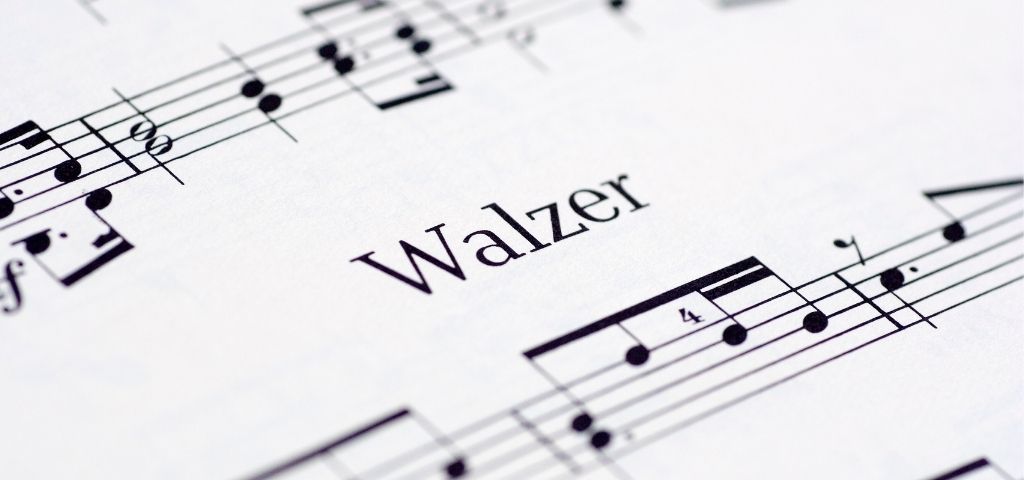優雅で上品なイメージのクラシック音楽。なかでも、貴族の舞踏会を連想させる“ワルツ”は特に華やかに感じられます。
クラシック音楽にあまり親しみがない人でも、ワルツなら楽しく聴けることも多いですよね。
そこでこの記事では、クラシック音楽初心者さんでも楽しめる「ワルツの名曲」を10曲厳選してお届けします!
目次
クラシック音楽の中でのワルツの歴史

ワルツといえば、貴族がダンスフロアで優雅に踊るイメージがありますね。
ですが、もともとワルツは「男女の距離が近すぎる」という理由で禁止されていました。
ワルツが流行る前(音楽史でいうとバロック時代)は「メヌエット」「ガボット」などが主流。
参考:クラシック音楽のメヌエットって何?メヌエットの名曲5つを紹介

へみ
男女が手を取り合うくらいの距離の踊りで、フランス革命直前の「ロココ調」っぽいダンスですね。
ワルツが広まったのは1800年代、音楽史でいうロマン派時代です。
1814年のウイーン会議(ナポレオン軍が敗れた後のヨーロッパ国境を話し合う会議)で、各国の代表たちが当時民衆の間で流行っていたワルツを夜な夜な踊り「会議は踊る、されど進まず」という名言が生まれました。
それをきっかけにヨーロッパ各地にワルツが広まり、さらに貴族の間でも流行しはじめたというワケ。
意外にもワルツの始まりは貴族ではなく、ウイーンの民衆から始まったジャンルなんです。
【オーケストラ編】クラシック音楽のワルツ名曲12選

それでは、クラシック音楽界でも特に有名なワルツを紹介していきます!

へみ
正直、オーケストラで有名なワルツというとほとんどがシュトラウス2世の作品になってしまうので、バランスよく選別しました
シュトラウス2世の作品については、別記事「クラシック音楽のヨハン・シュトラウス2世ってどんな人?代表曲と半生」を参照ください♪

あや
オーケストラで有名なワルツというと、ほとんどが1800年代のウィーンで作られたワルツか、バレエ音楽の中のワルツです。
民衆から貴族に広がってきた頃のワルツ、ということで、どのワルツも華やかで気分がアガる曲ですよ。
ヨハン・シュトラウスⅡ世:美しく青きドナウ
曲名を知らなくても、おそらく誰もが1度は耳にしたことがあろう曲です。
ウイーンでは毎年元旦に国営放送やニューイヤーコンサートで流れることもあり「第二の国歌」とも呼ばれるほど!
ウィンナ・ワルツの代表曲でもあり、二拍目を意図的に早めて演奏する「ウィーン風」の音源がほとんどです。
ハチャトゥリアン:仮面舞踏会
アルメニア人作曲家、ハチャトゥリアンのワルツです。
戯曲「仮面舞踏会」に合わせて作曲された曲のうちの1曲で、仮面舞踏会で出会う男女たちの数奇な恋愛模様が連想される曲調です。
ワルツといえば華やかで優雅なものが多いですが、戯曲「仮面舞踏会」がバッドエンドを迎えることもあり独特の暗い雰囲気があります。

へみ
ダークで大人な雰囲気があるということで、ハロウィンクラシックを特集した記事でも紹介させていただきました♪
ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ
ダンスフロアではなく、氷の上で優雅に滑る様子が表現された曲です。
作曲家のワルトトイフェルは、ワルツが流行った当時の市民から絶大な人気を誇っていました。が、現在はあまり知られていません。

へみ
このスケーターズ・ワルツも、昨今のヨーロッパではメジャーなコンサートピースではないようです。
ですが日本では学校やTVで聴く機会が多く、冬のワルツのイメージにぴったり。クリスマスパーティーでクラシック音楽を流すのにもいいですよね。
アンダーソン:ワルツィング・キャット
アメリカの作曲家、アンダーソンのワルツ。クラシック音楽初心者さんや猫ちゃん好きの方にもおすすめです。
タイトルどおり、猫がニャーオと鳴いているようなヴァイオリンの掛け合いが素敵♪
ちなみにタイプライターやブルー・タンゴなど、アンダーソンの名曲はこちらの記事でも紹介しています。
チャイコフスキー:くるみ割り人形より「花のワルツ」
チャイコフスキーのバレエ音楽の中で、最も有名な1曲である花のワルツ。
ロシア人のチャイコフスキーらしく、華やかさの中にもどこか憂いを帯びたメロディがなんとも美しいですよね。
個人的に、中間部のヴィオラチェロが奏でる「ちょっと悲しい」部分が、心揺さぶられる感じでイチオシです。
ヨハン・シュトラウスⅡ世:春の声
シュトラウスⅡ世の晩年の名作です。
演奏会後の余興の時にさっと書き上げた1曲なのに、今でも世界各国で演奏されているのが驚きですよね。
もとはコロラトゥーラ・ソプラノとオーケストラ伴奏のスタイルで作曲されています。
レハール:オペレッタ「メリーウィドウ」よりワルツ
オーストリア出身の作曲家、レハールのワルツです。
オペレッタ(喜歌劇)の中で使われているワルツなので、全体に物語性が感じられるような1曲。
莫大な遺産をもつ未亡人の主人公と、彼女のことがまだ好きな元カレが、ケンカをしながらワルツを踊るシーンで使われています。
ヴェルディ:オペラ「椿姫」より 乾杯の歌
ワルツとして書かれたものではないのですが、華やかなデュオはワルツ感満載!
今から社交の場が始まるよ!という場面なので「嫌なことは忘れて、愛におぼれましょう」という歌詞もワルツのコンセプトと似通ったものがあります。
参考:クラシック音楽でワインが美味しくなる!優雅&華やかな名曲でワインを楽しもう
ショスタコーヴィチ:ワルツ第2番
哀愁を帯びたメロディですが、どこか陽気さが感じられる、なんともロシアらしいワルツです。
ショスタコーヴィチはスターリンの粛清から逃れるために、長らく思うような作曲活動ができていませんでした。
こちらの曲はスターリンの死後約2年が経って発表されたもの。やや開放的な部分が見られるのは、そのせいでしょうか。
チャイコフスキー:白鳥の湖よりワルツ
バレエ音楽は、もともと「踊りの付属品」くらいの位置づけで重要視されていませんでした。
そんなバレエ音楽の地位を押し上げたのが、チャイコフスキーの白鳥の湖です。
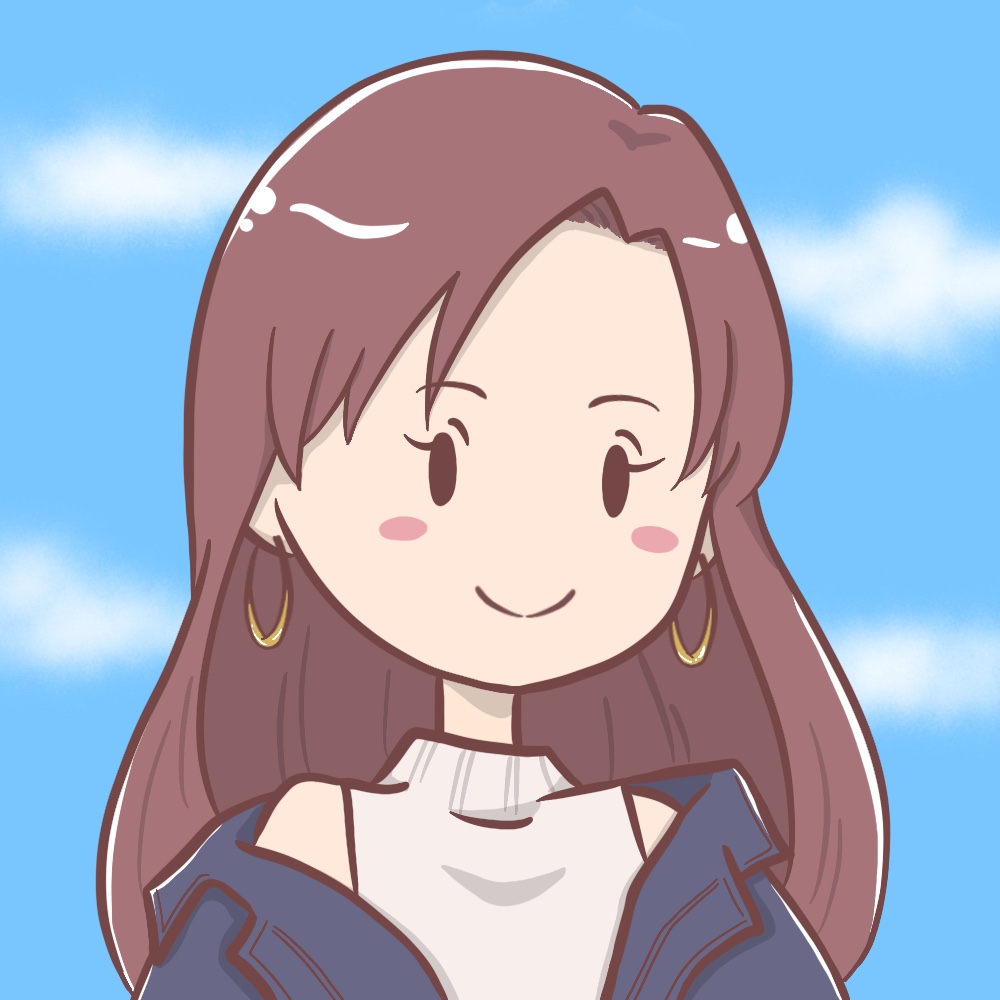
へみ
音楽と踊りどちらも楽しめる一大エンターテインメントとなりました
チャイコフスキーのワルツはただ華やかなだけではなく、社会風刺的な要素や多民族な要素が魅力的です。
ラヴェル:ラ・ヴァルス
「ワルツ全盛期」である1800年代風に、という思いを込めて作られたラ・ヴァルス。
英語の直訳で「ザ・ワルツ」という通り、パッと聴いた感じではヨハン・シュトラウス2世の雰囲気があります。

へみ
ですが、聴き進めていくと「ザ・ラヴェル」です!
大人数のオーケストラでしか再現できない「究極のクレッシェンド」や、ジャズライクな部分が出てきたりと、聴きごたえ抜群の1曲となっています。
参考:【クラシック音楽】モーリス・ラヴェルってどんな人?代表曲とエピソード
プロコフィエフ:シンデレラのワルツ
バレエ音楽「ロミオとジュリエット」で知られるプロコフィエフですが、ロミジュリの3年後から新作「シンデレラ」の依頼を受け、作曲を開始します。
シンデレラもプロコフィエフの世界観が発揮されている作品ですが、ロミジュリに比べてロマンティック度がケタ違い!
この「シンデレラのワルツ」も、まるでファンタジー映画を見ているような不思議な感覚にさせてくれます。
【ピアノ曲編】クラシック音楽のワルツ名曲8選
ピアノ曲のワルツというと、実際に踊りで使われるものとは少し違う性格を持ちます。
特に「ショパン」「シューマン」が多く作曲したのですが、ピアノ曲のワルツは”性格的小品”のうちの1種となります。

へみ
ノクターン(夜想曲)やラプソディー(狂詩曲)、など、1つのコンセプトを持つ小さな曲の1種にワルツ(円舞曲)があります。
基本は3/4拍子の曲で、人がリズムに乗って踊れるくらいの中くらいの速さ。
それでいて、ピアノ曲は「うっとりできる」「優雅な」雰囲気を持つことが特徴です。
ショパン:華麗なる大円舞曲
ショパンが初めて出版したワルツが、この華麗なる大円舞曲だと言われています。
故郷ポーランドを離れ、一人修行に出てきたウィーンで当時流行っていたのがウインナーワルツ。
ショパンはすぐに自分の感性とマッチさせ、華やかさと繊細さを同居させたワルツを数々生み出していきました。
ショパン:別れのワルツ
ショパンのワルツは踊るためというより「聴き入る」曲ですよね。
この別れのワルツも「短調で始まり長調で終わる」和音の移り変わりが絶妙で、不思議な心地よさを生み出しています。
すっと心が静かになるので、集中力を高めるクラシックの特集でも紹介しました!
リスト:メフィスト・ワルツ
メフィストとは、ヴァイオリンの名手の皮を被った悪魔のこと。
そのメフィストが主人公ファウストとともに酒場にやってきて、メフィストがヴァイオリンを弾いて酒場の人々が浮かれている隙にファウストが一人の踊り子とそっと抜け出していく…
そんなストーリーが見事に再現されたワルツです。

へみ
リストらしい超絶技巧もさることながら、ストーリーを表現する表現力も求められる超難曲です。
参考:フランツ・リストの名曲5選!クラシック音楽界きってのモテ男の晩年までたどる
ブラームス:ワルツ第15番
ブラームスのワルツのうち、最も有名な曲です。
舞踏会のワルツ、という華やかな曲調ではなく、自然の中を歩いているような安心感や落ち着きがあります。
終止の音が「和音の真ん中の音」というのはブラームスがよく使う手法なのですが、どこかに想いを馳せるような不思議な気分にさせてくれますね。
参考:【晩秋に聴きたい】ブラームス珠玉の名曲5選!クラシック音楽初心者でも感動できます
ドビュッシー:ロマンティックなワルツ
「月の光」が組まれている”ベルガマスク組曲”と同時期に作曲されたワルツです。
ベルガマスク組曲が東洋の旋律やバロックダンスを組み合わせているのに対し、こちらのワルツは同世代のサティやフォーレの影響が色濃い感じ。
当時流行っていたサロンミュージックのような気軽さを持ちながら、人々をぐっと引き込む色彩感が魅力ですよね♪
参考:クラシック音楽のドビュッシーってどんな人?名曲7選を半生とともに紹介
ショパン:子犬のワルツ
言わずと知れたショパンの名曲ですね。
人間が踊るワルツにしてはテンポが速いのですが、これは「恋人が飼っていた仔犬が、自分の尻尾を追いかけている様子をワルツに見立てた」からです。
このワルツは即興で作られたというから驚きですよね!
参考:テンポの速いクラシック音楽20選!初心者でも退屈にならない楽しい曲
シューマン:ドイツ風ワルツ
1分程度の短いワルツですが、シューマンの情感がたっぷり詰め込まれています。
Op.9(作品9番)という事で、シューマンの本当に若い時の作品。
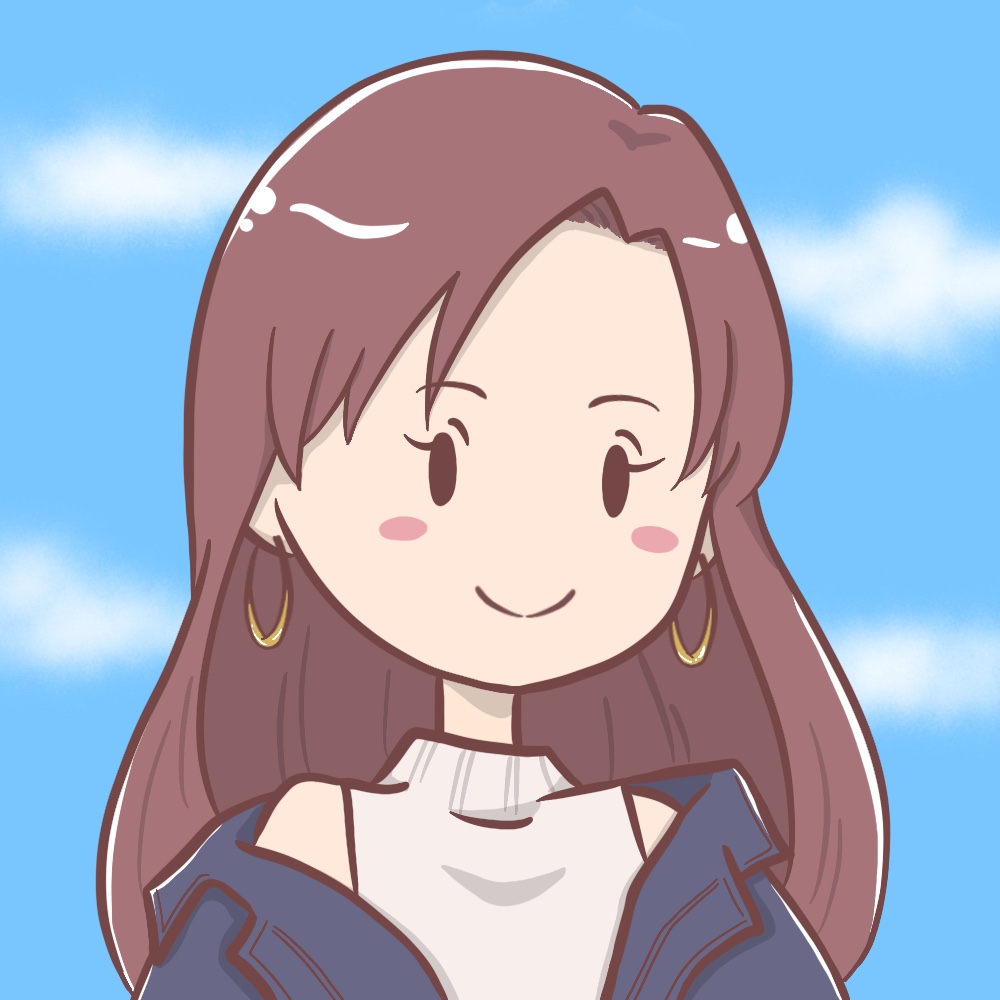
へみ
実はこのころのシューマンは、のちに結婚するクララ「ではない」人物に恋をしていて、その女性に贈られたワルツなんです
恋する女性の出身地を(A、Es、C、H)とアルファベットに分解し、それを散りばめた「クイズ形式」のワルツなので、ぜひ楽譜と一緒に楽しみたいですね。
サティ:ワルツ=バレエ
「ジュ・トゥ・ヴ」と同じ頃、サティ初期に作曲されたワルツです。
パリ音楽院を「退屈だ」と退学したサティは、カフェや酒場で「家具のような(さらっと聞き流せるような)音楽」を演奏するようになります。
洒落た雰囲気を持ちながら、BGMとしても最適なワルツですよね。
クラシック音楽でワルツを楽しむポイント

ワルツの始まりであるウインナーワルツは、あえて二拍目を早めに演奏するスタイル。
なので、音源によって拍の取り方が微妙に異なってきます。
結構好みが分かれるので、自分に合った音源を探すのが楽しいですよ。
もしもどの音源を聴くか迷ったら、NHK交響楽団など日本のオーケストラの音源を選ぶと後悔が少ないです。
【クラシック音楽】どの演奏家のCDを聴けばいい?初心者向けの選び方のポイントを解説
クラシック音楽でワルツを楽しむならAmazonミュージック
クラシック音楽の中でも、ワルツは人気のジャンルです。
そのため「ワルツ全集」などオムニバス系のCDも多くて、音源を選ぶのが大変!
自分好みの音源でプレイリストを作るなら、最近人気の「音楽サブスク」を選ぶのが◎です。
当サイトおすすめの音楽サブスクが「Amazonミュージック」で、クラシック音楽を含め1億曲以上が聴き放題!
月額料金は1080円とお手頃で、プライム会員ならさらに安く880円となります。
今なら3ヵ月無料でお試しできるので、ぜひこの機会にクラシック音楽を楽しんでみてくださいね。