哀愁あるメロディを吹かせたら右に出るものはいないオーボエ。
表情豊かに歌い上げる一方、音域や音量に制限があって人一倍苦労が多いのもオーボエなんです。
そんなオーボエの魅力や名曲を徹底解説します♪
目次
オーボエってどんな楽器?

オーボエはダブルリードと呼ばれる「2枚のリードの隙間に息を吹き込んで音を出す」楽器です。
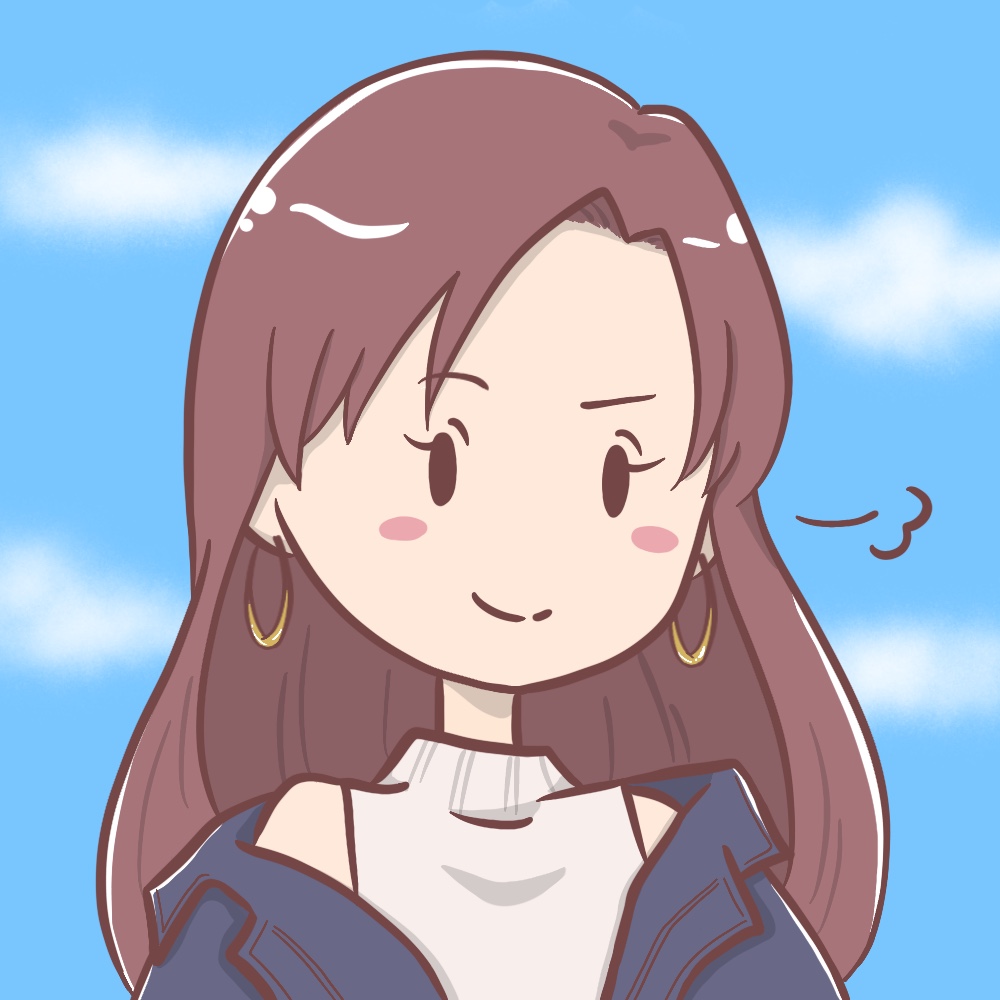
へみ
リードとリードの隙間は1mmないくらい、奏者から出る息はほとんど楽器に入っていかないことになります。
1分近くロングトーンできるのが強みな一方、息継ぎをする際には一度息を吐いてから吸う必要があるので奏者にはかなり負担がかかります。
ほかにも
- しんどい割に大きな音が出ない
- 他の楽器に比べて音域が狭い
- 楽器を固定するのが唇のみのため、音程が安定しづらい
- リードの質によって音色や音程が大きく左右される
など、オーボエ奏者には苦労がたくさん。
そのため、オーボエはギネスブックに「世界一難しい楽器」として登録されています。
オーボエの音色と音域
オーボエの音域はB♭3(ピアノの基本のド、より2つだけ低い音)から約3オクターブくらい。だいたいフルートと同じ音域ですね。
ですが、実際にオーケストラで使われるのは約2オクターブの間くらい。
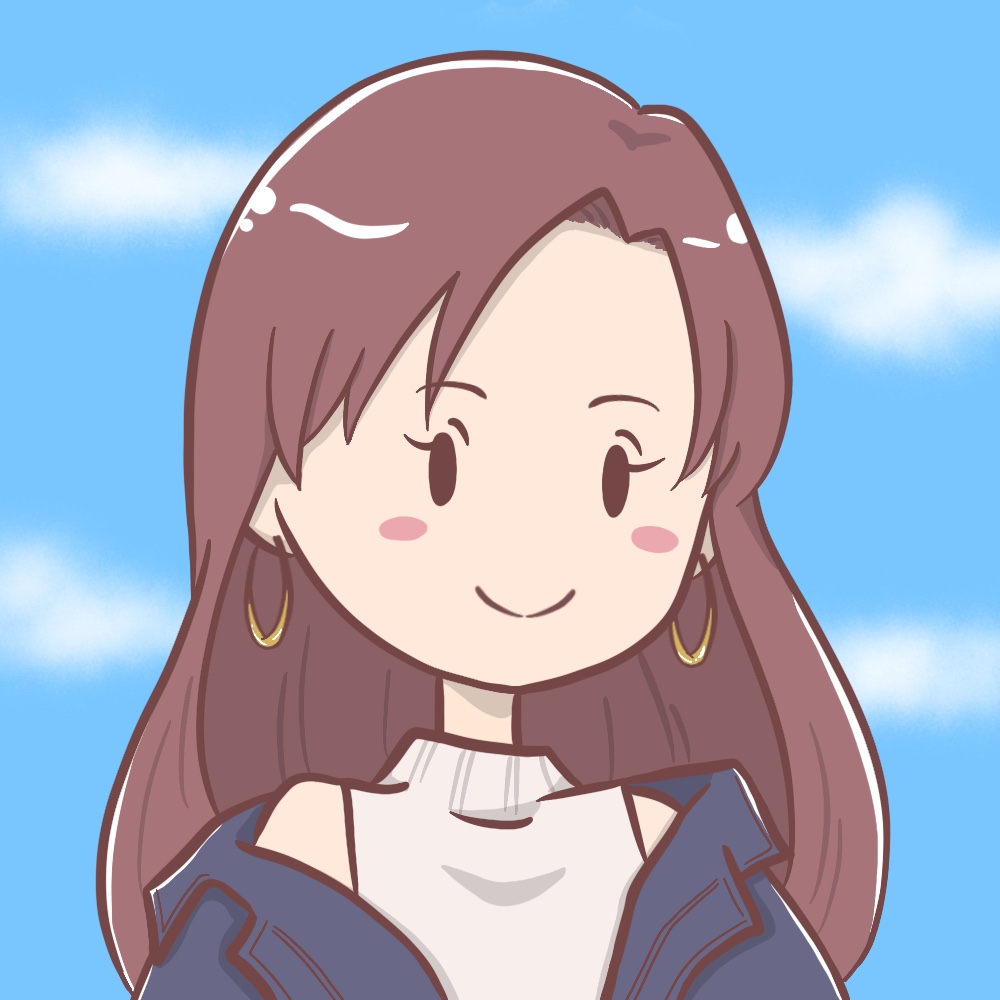
へみ
というのもオーボエは美しく響く音域がかなり限定されていて、さらに音量も小さい楽器だからです。
低音域は渋みがある暗い雰囲気の音色、高音域は機械的で少しカドがある音色となるので、聞かせどころはどうしても中音域に偏ります。
そのぶん中音域は、哀愁と華やかさが行き来する「絶品」の音色です。
オーボエのオーケストラでの役割
音量と音域が限られるオーボエは、メロディの割合が多め。
ですがその限られた音域が非常に美しいので、ここ一番!の美しい旋律を担当する事が多いです♪
音色は同じリード楽器のファゴットやクラリネットと相性が良いので、木管パートでのユニゾンでも活躍します。
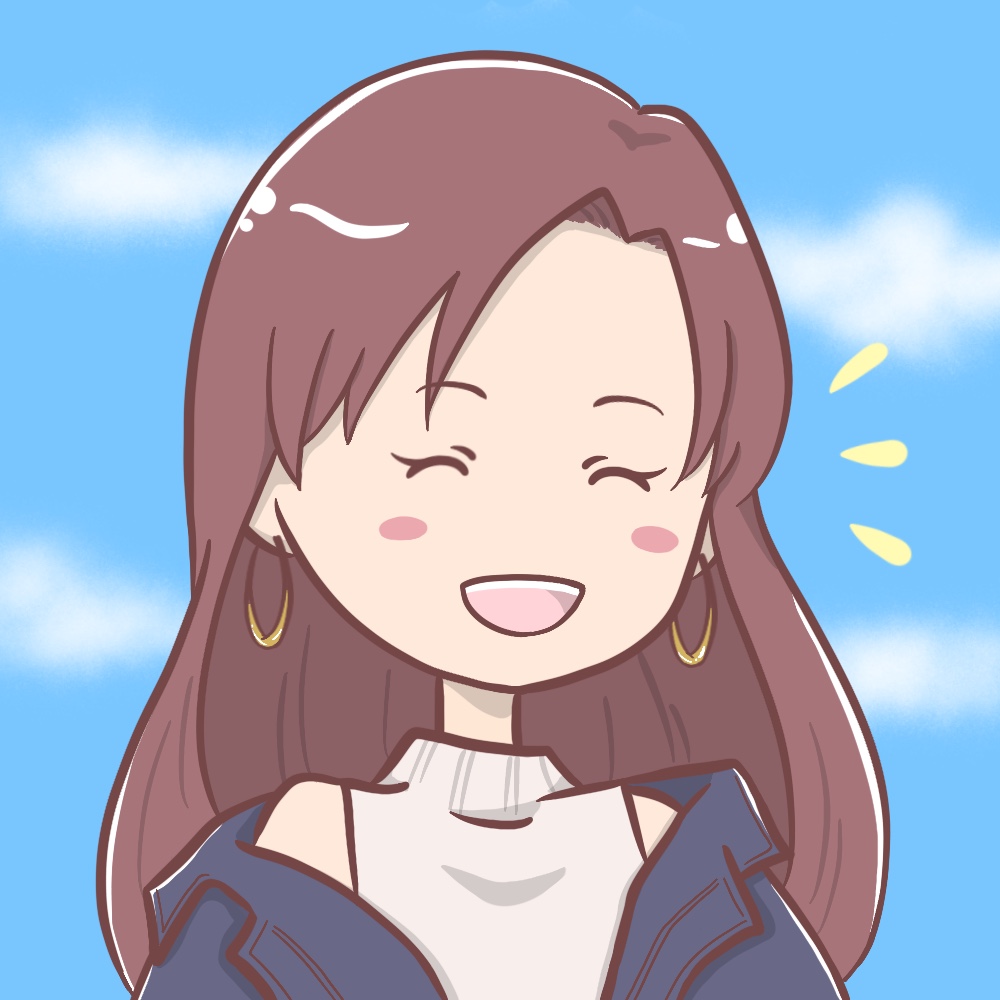
へみ
オーケストラでの木管ユニゾンは、温かみがあって「牧歌的」「穏やかな自然の表情」といった表現が得意です♪
オーボエでチューニングするのはなぜ?
もう一つ、オーボエの重要な役割は「チューニング」です。
オーケストラの中で一番最初に音を出すのがオーボエ。次に音を出すのがヴァイオリンの首席奏者(コンサートマスター)、そのあと全員が一斉に音を出してチューニングします。
オーボエは他の楽器と違い「管が分解できない」楽器なので、細かな音程の上下が少ない安定した楽器だから、というのが一説にあります。
オーボエの名曲10選

それでは、オーボエの名曲やオーボエが活躍するオーケストラ曲を10個紹介します!

へみ
歴史ある楽器のオーボエなので、様々な時代の楽曲が存在するのも魅力の1つです♪
モーツァルト:オーボエ協奏曲第1番
オーボエの主要レパートリーで、「のだめ」など音楽漫画、ドラマなどでも登場頻度が高い曲です。
オーボエが一番よく響く音域が駆使されている1楽章、オーボエの叙情的な音色が楽しめる2楽章、軽く飛び回るような表情が魅力の3楽章。
オーボエの魅力が余すことなく盛り込まれているので、オーボエの事を知るのにもぴったりです。
チャイコフスキー:白鳥の湖より「情景」
バレエ音楽「白鳥の湖」と言えばこの曲。
オーボエの長いソロから始まり、物語の悲劇的部分や王子とプリンセスの心情がぎゅっと詰まっています。

へみ
シンプルなメロディですが、長い息で悠々と歌い上げられる楽器はオーボエのほかにありません。
寂しさの中にも「内から気持ちがあふれ出る」感覚になれるのも、オーボエの音色だからでしょう。
コジ・ファン・トゥッテ:モーツァルト
こちらもオーボエソロで始まる曲です。
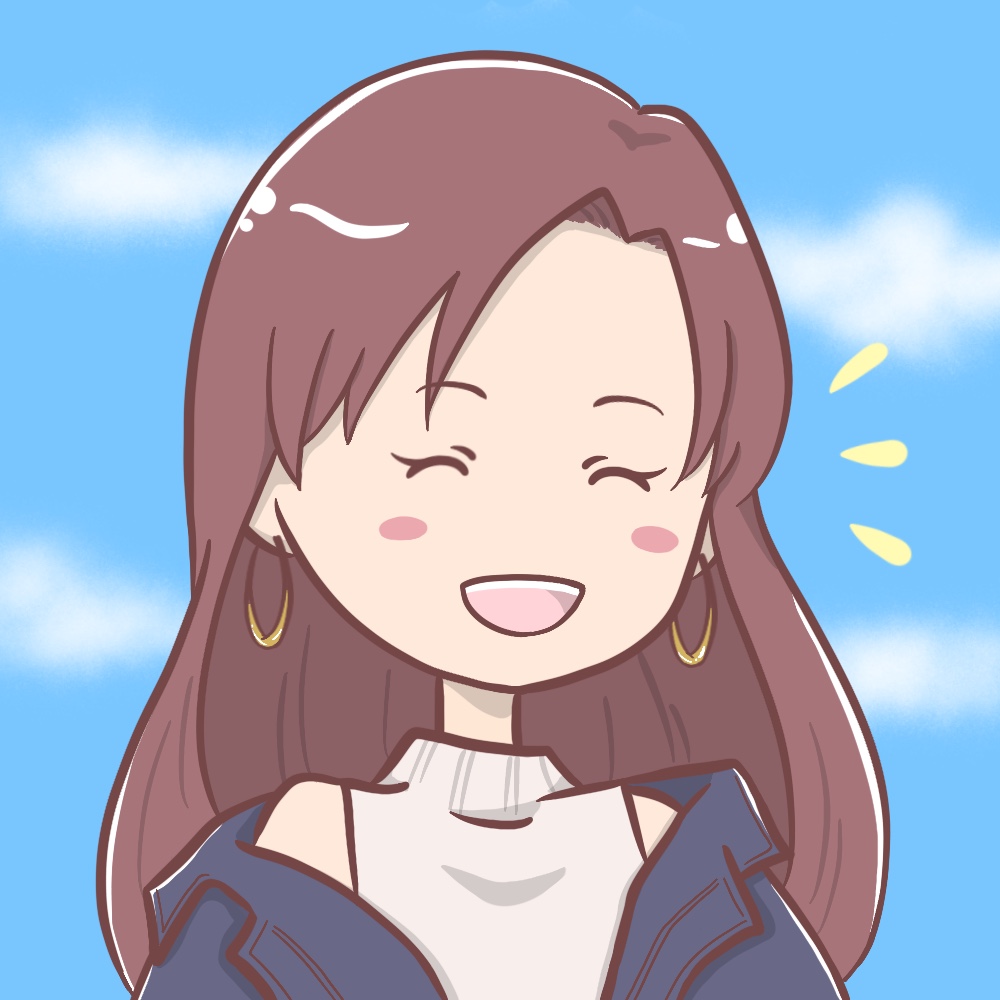
へみ
オペラやバレエ音楽って、オーボエソロで始まるとすごくドラマチックでわくわくしますよね♪
序曲の中盤~終盤にかけては、オーボエとフルート、クラリネットなど木管楽器同士での掛け合いが楽しいです。
まるで物語の恋人たちのように、明るく軽快に次々と展開が変わっていきます。
マルチェッロ:オーボエ協奏曲
1700年代はじめ、バッハが活躍している頃のバロック時代に書かれたオーボエ協奏曲です。
構成は通常のオーケストラ+オーボエ、ではなくて、弦楽4重奏とチェンバロ+オーボエです。
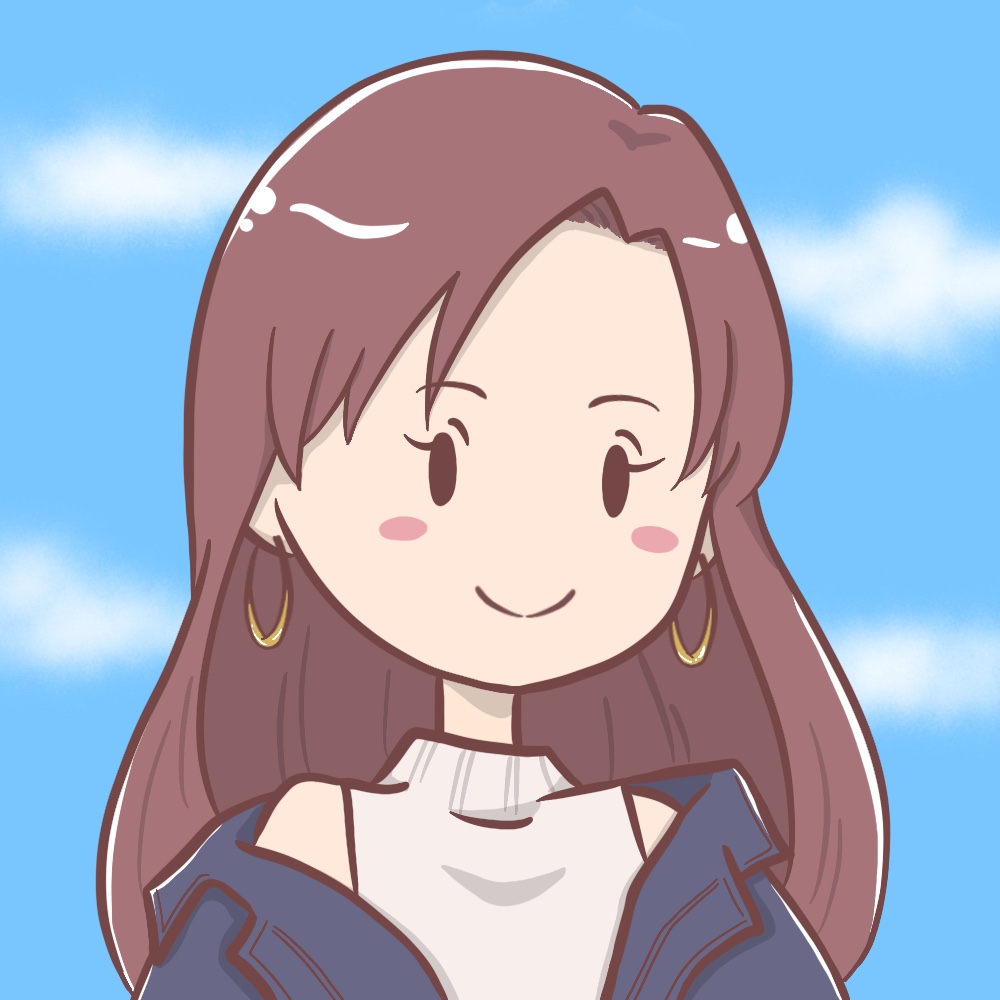
へみ
大規模なオーケストラと違って、繊細なオーボエをそっと支える弦楽アンサンブルが絶妙なバランスを保っています
一番有名なのは2楽章で、映画「ヴェニスの愛」で使われたことで有名になりました。
R.シュトラウス:オーボエ協奏曲 二長調
1945年、終戦直後に書かれたオーボエ協奏曲なのですが、どこかモーツァルトの時代の「正統派」音楽のようにも感じられます。

へみ
この曲はR.シュトラウスが81歳の時の作品なのですが、年齢を重ね、さらに戦争も経験したことで辿り着いた美しさがありますよね
オーボエの一番の魅力「美しいメロディを奏でる」というのに特化した協奏曲で(もちろん技巧的な部分もありますが)どこを切り取っても美しい旋律を聴くことができます。
シューマン:3つのロマンス
シューマンの作品はどれも「少し憂いを含んだ」ような作品が多いのですが、それがオーボエの音色に見事にマッチ。
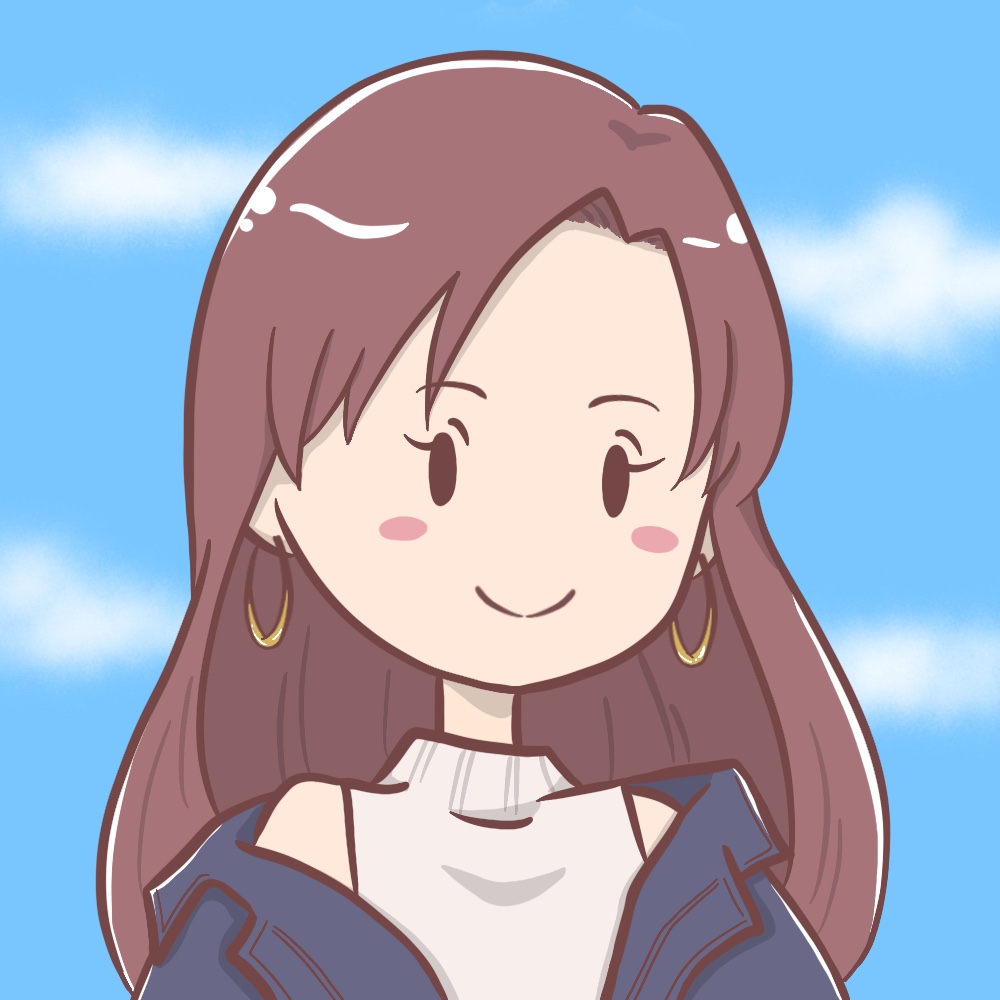
へみ
歌曲も多く残しているシューマンなので、どこかソプラノの歌曲風なのも頷けますね。
シューマンの曲の中でもかなり人気の作品なので、他の楽器で演奏される事も多い楽曲です。
曲全体通してメロディアスなのですが、和音の移り変わりが頻繁にあるので聴いていて飽きません。
ヴィヴァルディ:オーボエソナタ
チェンバロが伴奏のオーボエソナタなので、触ったら壊れてしまいそうな繊細さがあるソナタです。

へみ
ヴィヴァルディと聞くと「春」をイメージする人が多いと思うので、全然違う雰囲気にびっくりするはず!
2楽章は結構テクニカルな部分が多いのですが、作曲された時代のオーボエは今よりもっと難しい楽器だったので当時の奏者は「超絶技巧曲」として練習していたかもしれません。
サン=サーンス:オーボエソナタ
サン=サーンス晩年の作品で、同じ年に書かれたオーボエソナタ・クラリネットソナタ・バスーンソナタを3つ合わせて「白鳥の歌」とも呼びます。
というのもこの晩年の作品群は洗練された、澄んだ響きの美しい作品ばかり。このオーボエソナタも、クラシック界の清純派とも取れる透明感があります。

へみ
個人的には2楽章が大好きで、この時代(フランス印象派)らしい色彩豊かな和声にうっとりします
バッハ ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲
どこか「ブランデンブルク協奏曲」を思わせるような重厚な協奏曲です。
弦楽器が分厚い和音を奏でるその上に、ヴァイオリンとオーボエの掛け合いが涼しい顔で行われています。
2楽章は伴奏がピツィカート(弦を指で弾く奏法)なので、ヴァイオリンとオーボエの掛け合いが分かりやすいです。
風笛(あすかのテーマ)
NHK朝の連続テレビ小説「あすか」のテーマソングです。

へみ
クラシック音楽としては「邪道」かもしれませんが、個人的にオーボエの曲でこれは外せません
オーボエがオクターブ近く上に跳躍する際、なんとも言えない滑らかで澄んだ響きになるのですが、それが上手く活かされていると感じる曲です。
オーボエには仲間がたくさん!オーボエ群の名曲7選
実は、オーボエにはサイズ違いで様々な楽器が存在します。
オーボエはC管、短3度低いA管が「オーボエダモーレ(通称愛のオーボエ)」、さらに長3度低いF管が「イングリッシュ・ホルン」です。

へみ
それぞれソロ曲は少ないものの、オーケストラで存在感あるソロがある曲がたくさん♪
オーボエの名曲だけを紹介するのはもったいない!という事で、オーボエファミリーの名曲も紹介いたします。
【オーボエ・ダモーレ】ラヴェル・ボレロ
かの有名な「ボレロ」のソロ5番手として登場しているのが、オーボエダモーレです。
オーボエっぽい響きなので混同されがちですが、ややこもった温かい音なので意識すれば聴き分けられるでしょう。
ちなみにオーボエファミリー(オーボエ・オーボエダモーレ・イングリッシュホルン)が全員でメロディを奏でる部分もあるので、ぜひ探してみてください。
参考:【クラシック音楽】モーリス・ラヴェルってどんな人?代表曲とエピソード
【イングリッシュホルン】ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」第2楽章
日本では「家路」でおなじみのメロディは、イングリッシュホルンのソロで提示されます。
音域的にはオーボエでも演奏できるメロディですが、ドヴォルザークはあえてイングリッシュホルンを指定。
低い音でも渋みが出にくく、甘く温かい音で演奏できるので、今ではイングリッシュホルン以外には考えられませんよね。
【イングリッシュホルン】ボロディン 韃靼人の踊り
フルートのソロが物語の始まりを告げ、はかないオーボエソロが始まります。
このオーボエソロと、続くイングリッシュホルンのメロディは「世界一美しいメロディ」と呼ばれ、ファンが多い名曲。
歌劇のなかの1曲ではありますが、単体で演奏機会が多い曲です。
参考:【泣ける】美しいメロディのクラシック音楽10選!プレイリストに加えたい名曲たち
【オーボエ・ダモーレ】バッハ オーボエダモーレ協奏曲イ長調
オーボエ・ダモーレは、もともと1700年前後によく演奏された「古楽器」です。
特にバッハが好んで編成に加えていて、マタイ受難曲を始めとする大曲でオブリガートでよく登場します。
この時代の協奏曲は、ソロ楽器と伴奏楽器がはっきり分かれていないことも多いのですが、この協奏曲はがっつり「オーボエダモーレのための曲」で、モーツァルトの時代の古典派ともとれるほど。
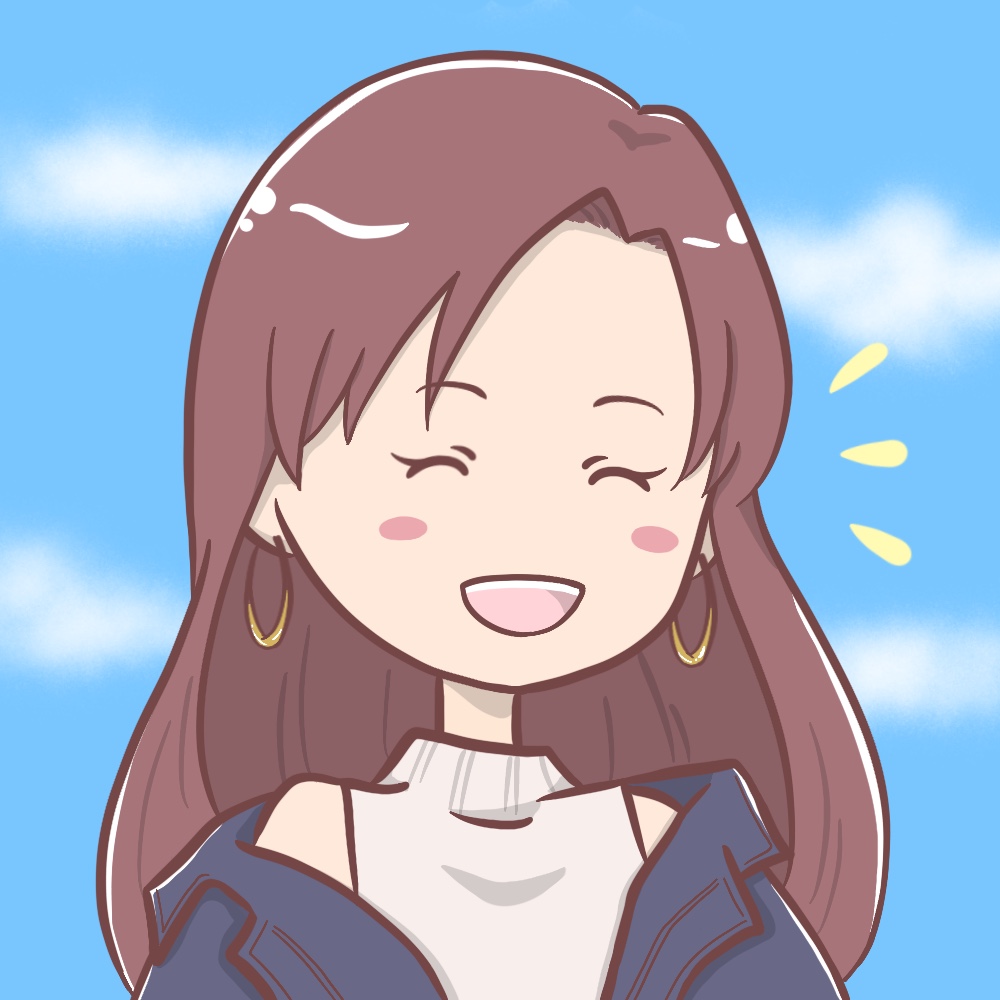
へみ
バッハのオーボエ愛が感じられますよね♪
【イングリッシュホルン】ベルリオーズ 幻想交響曲 第3楽章
副題に「野の風景」と付いている楽章で、中間部にオーボエとイングリッシュホルンのかけあいがあります。
2人の羊飼いを表現していて、イングリッシュホルンが舞台上で演奏するのに対しオーボエは舞台裏で演奏。
舞台裏の演奏はタイムラグがあり、一歩間違えると大崩壊!演奏者はかなり気を遣う場面です…
参考:フランス音楽で有名なクラシック作曲家7人!印象派以外の音楽家も紹介
【イングリッシュホルン】チャイコフスキー くるみ割り人形より「アラビアの踊り」
この曲でイングリッシュホルンが登場するのは後半部分。
オーボエのアラビア風のソロが終わった直後に同じメロディをオクターブ下で演奏しているのがイングリッシュホルンです。
アラビア風のメロディは、ダブルリードでないと雰囲気が出ないですよね…!
参考:【クラシック音楽】ロシアの作曲家はどんな人がいる?ロシア5人組の関係とは
【イングリッシュホルン】ラヴェル スペイン狂詩曲
第4曲「祭り」でイングリッシュホルンの幻想的なソロが登場します。
第4曲は全体に情熱的で、リズムが勢いよく刻まれていく楽しい曲なのですが、イングリッシュホルンが奏でられる中間部は「小休止」の部分。
お祭りムードから一時離れて、けだるいムードが漂うのがまたお祭りらしいですよね。
参考:【クラシック音楽】モーリス・ラヴェルってどんな人?代表曲とエピソード
オーボエの名演奏を聴くならAmazonミュージック
クラシック音楽が始まって以来ずーっとオーケストラの一員であるオーボエですが、意外とレパートリーが少ない楽器なんです。
そんなオーボエの名演奏を探すなら、クラシック音楽も聴ける「音楽サブスク」がおすすめ!
当サイトおすすめの音楽サブスクが「Amazonミュージック」で、クラシック音楽を含め1億曲以上が聴き放題!
月額料金は1080円とお手頃で、プライム会員ならさらに安く880円となります。
今なら3ヵ月無料でお試しできるので、ぜひこの機会にクラシック音楽を楽しんでみてくださいね。


















