クラシック音楽を語る上では欠かす事ができないロシア音楽ですが、意外にも歴史は浅いジャンルとなります。
ロシアのクラシック音楽にはどんな特徴があるのか、代表的な作曲家とともに紹介していきます。
目次
ロシアのクラシック音楽の歴史

18世紀初頭までは世俗的な音楽が禁止されていて、いわゆる「バロック音楽」「古典派音楽」というジャンルではほぼロシアの名前は出てきません。
クラシック音楽が入ってきたきっかけは近代化政策によりサンクトペテルブルクが建都されたこと。1703年のことでした。
貴族的たちは西ヨーロッパの文化を積極的に取り入れ、オペラや舞踏会といった芸術を用いて社交の場を広げていきました。
ロシア5人組とは
もともとロシアには多様な民族音楽が根付いていたこともあって、クラシック音楽と民族音楽が融合して独自の発達を遂げていきます。
その「ロシア独自の音楽」を追求していたのが、ロシア5人組と呼ばれる音楽家集団です。
- ミリイ・バラキレフ
- ツェーザリ・キュイ
- モデスト・ムソルグスキー
- アレクサンドル・ボロディン
- ニコライ・リムスキー=コルサコフ
上記の5人組は、1860年代より活動を開始し、ロシアオペラや標題音楽を発展させました。
チャイコフスキーとバレエ音楽
一方、ロシア5人組と敵対する音楽家に指示していたチャイコフスキーは、5人組と距離を置きながら独自の世界観で次々と作曲していきました。

へみ
チャイコフスキーの一番の功績と言えば「バレエ音楽」です。
白鳥の湖やくるみ割り人形など、誰もが知る作品が今日でも人気なのはチャイコフスイキーの音楽があってこそ。
ロシア風のメロディを取り入れつつも、西欧やアジアの人々の心にも響く作品を多数残しました。
ピアニストとヴァイオリニストの台頭
ソ連時代には、エリート養成教育が進み数々の音楽家がロシアから生まれていきます。
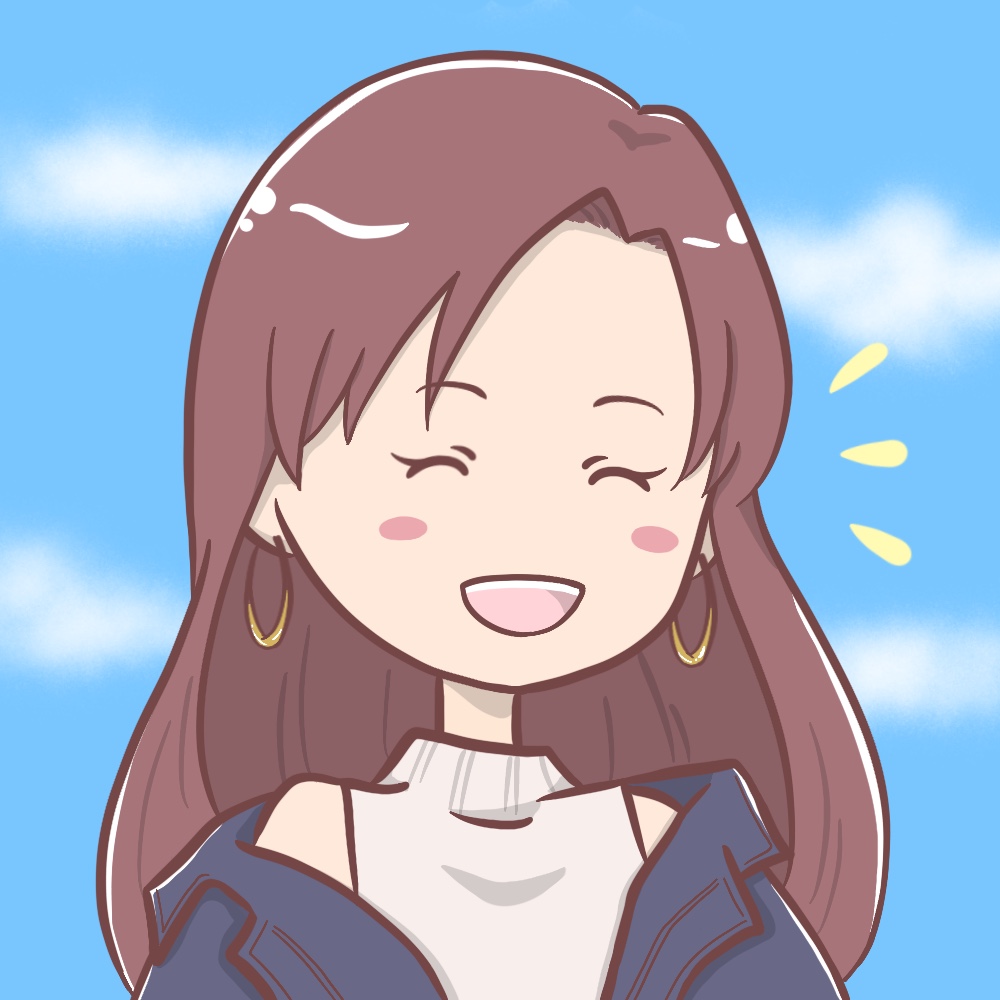
へみ
恵まれた体格や厳しい冬に耐えうる精神力もあって、現在でも有名なピアニストやヴァイオリニストはロシア出身の方が多いですね。
ラフマニノフやプロコフィエフといった、有名ピアニストが手掛けた曲も、ロシアの代表曲となっています。
ロシアの代表的なクラシック音楽作曲家10人

それでは、ロシアクラシック音楽界でも有名な7人を、代表曲とともに紹介していきます!
名前は分からなくても曲はかなり有名なものばかりなので、これを機に豆知識を増やしてみてくださいね。
①アレクサンドル・ボロディン(1833- 1887)
ロシア5人組のなかの一人ですが、実は本業は音楽家ではありません。

へみ
ボロディンは医師・科学者として優れた功績を残していて、本人曰く「日曜作曲家」でした。
頭脳もさることながら音楽的センスもずば抜けていて、交響曲は2番まで書き残されています。
ボロディンで一番有名なのが、オペラ「イーゴリ公」。世界一美しいメロディとして有名な「韃靼人の踊り」はこのオペラの中の一曲です。
残念ながらイーゴリ公が完成する前に急死してしまうのですが、ロシア5人組のリムスキー=コルサコフとグラズノフによって追記完成されました。
ロシア民謡の特徴である「ヨナ抜き音階」を上手く取り入れた、哀愁あるメロディ。ロシア・クラシックの発展に大きく貢献した人物の一人です。
②モデスト・ムソルグスキー(1839- 1881)
ロシア5人組の1人で、ロシアの伝統や民謡を守りたいという姿勢が強かった作曲家です。

へみ
ムソルグスキーもボロディンと同じく、本職は公務員の「掛け持ち音楽家」でした
歌劇を多く残しているのですが、ロシアの史実や人々の生活を忠実に表現しているほか、いわゆる「風刺的」な部分も見られます。
有名な楽曲は、ディズニー作品「ファンタジア」に出てくる”禿山の一夜”ですが、筆者のイチオシはピアノ組曲「展覧会の絵」です。
展覧会の絵は、ムソルグスキーの友人の画家が亡くなった後、彼の作品展を見て回るムソルグスキーの様子が表現されています。
曲ごとに拍子や表情が全く異なるのですが、それを”プロムナード”が繋いでいるので、実際に映像を見ているかのような錯覚に陥ります。
多くの作曲家にインスピレーションを与えたこの曲は、フランスのモーリス・ラヴェルをはじめとする編曲版も数多く残されています。
③ニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844- 1908)
ロシア文学や民謡、言い伝えなどをもとにした作品を数多く残したのがリムスキー=コルサコフです。
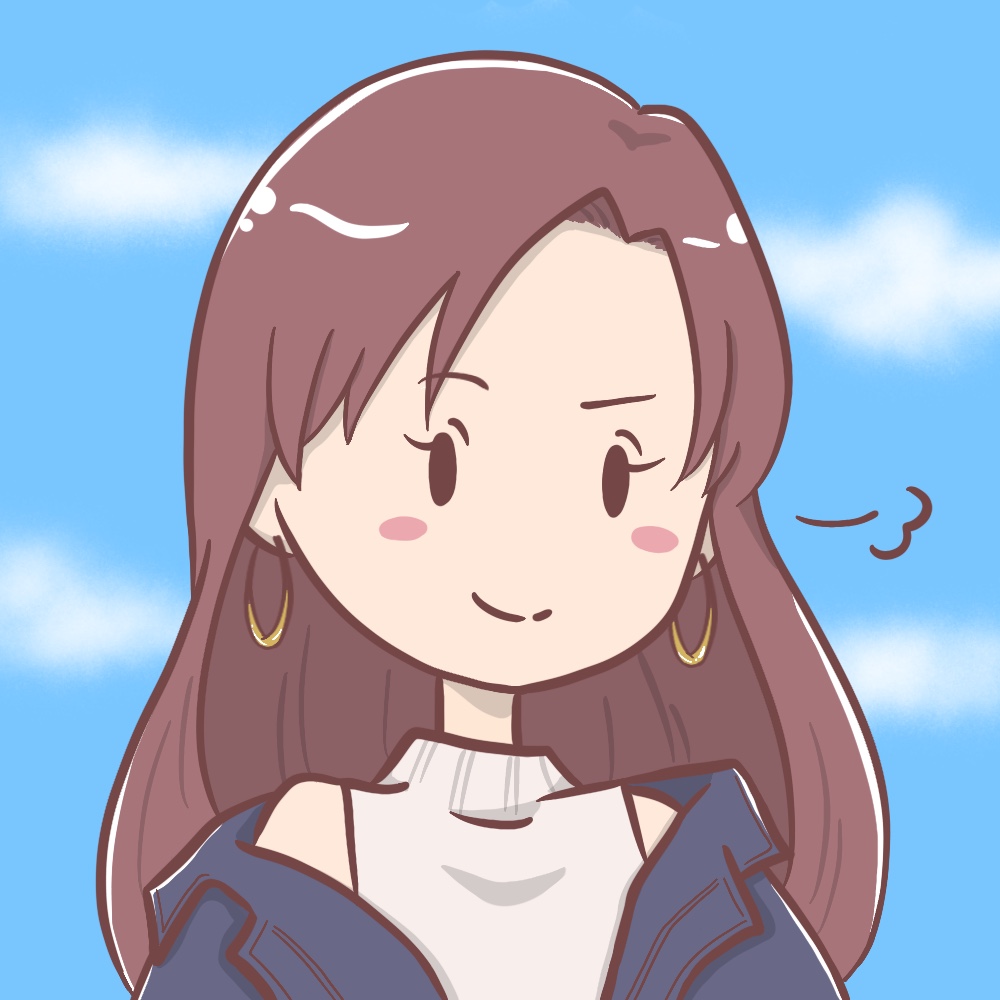
へみ
もともと音楽的教育は受けておらず、ロシア5人組となるまではなんと独学で作曲していたというツワモノ。
代表曲はアラビアンナイトを題材にした「シェヘラザード」で、鮮やかでエキゾチックな魅力が今日でも人気の作品です。
オーケストラの各楽器の魅力を最大限に引き出した作品で、ソロ楽器が奏でるそれぞれの主題が聴衆の想像力を掻き立てます。
④ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840- 1893)
もはや説明不要なほど人気で有名なチャイコフスキー。
バレエ音楽「くるみ割り人形」「白鳥の湖」や、7つの交響曲、ヴァイオリン協奏曲など、数々の名曲を残した作曲家です。
どこか懐かしいようなメロディと分かりやすい和音進行で、クラシック音楽初心者も聴きやすい音楽が魅力。
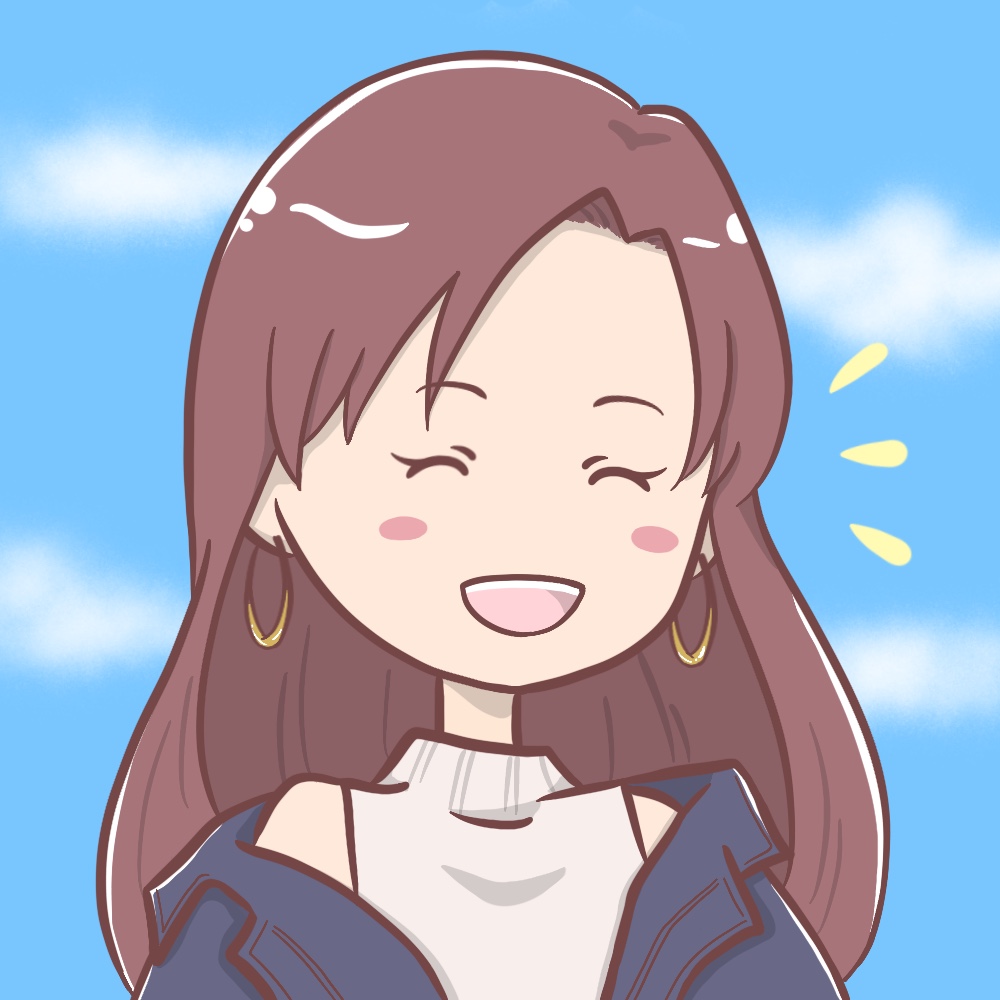
へみ
そんな親しみやすい音楽に「絶妙な装飾」を加えて、キラキラ華やかに仕立て上げるのがチャイコフスキーの特徴です。
バレエや歌劇の作品が特に人気で、ロシア文学が世界で評価されるきっかけを作った人物とも言えるでしょう。
参考:【クラシック音楽】ワルツの名曲10選!優雅な気分に浸れる楽曲を紹介
⑤アレクサンドル・ニコラエヴィチ・スクリャービン(1872- 1971)
あとに紹介するラフマニノフと、モスクワ音楽院時代の同級生だったスクリャービン。
即興演奏が得意で、ピアノではラフマニノフと1,2位を争うほどの技巧派でした。
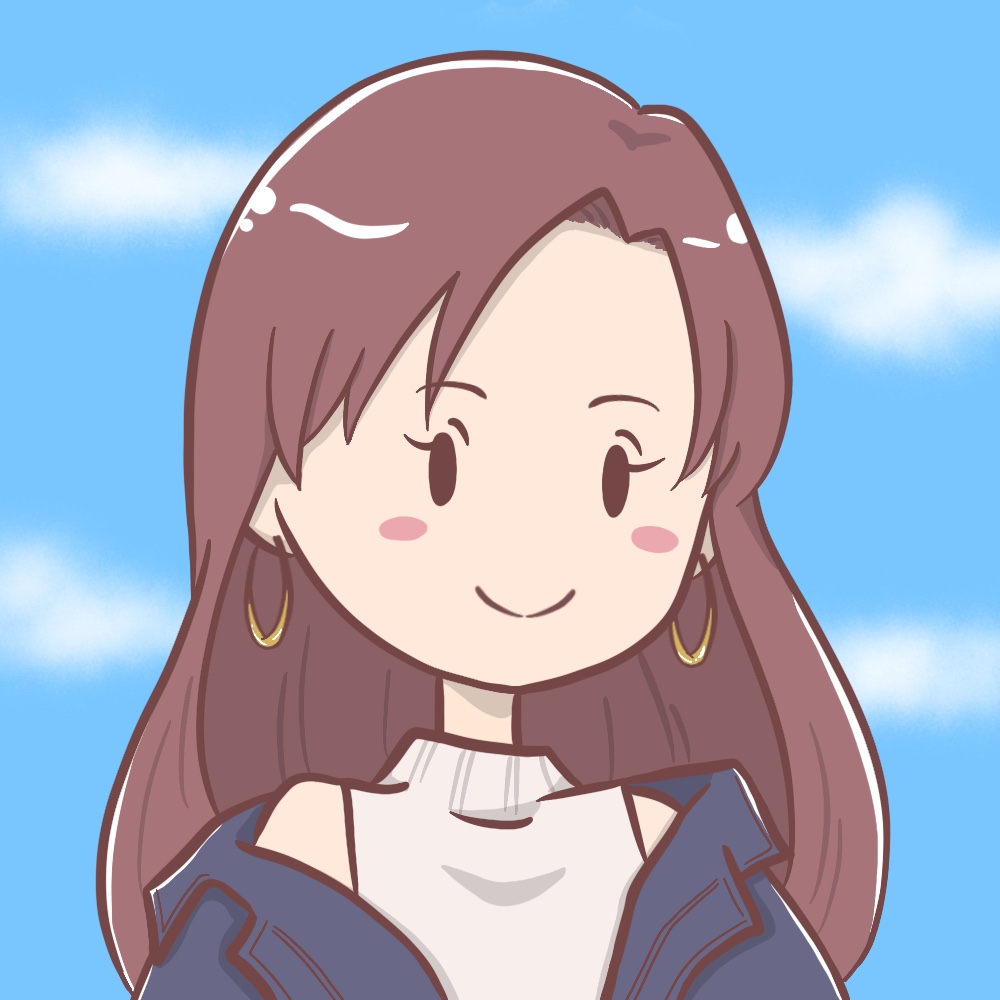
へみ
ですが、ドから1オクターブ上のラまで(13度)まで届くほどの手の持ち主だったラフマニノフに対し、スクリャービンはド~1オクターブ上のミ(10度)がきつかったくらい、手が小さかったんです。
小さい手で難曲を練習し続けた結果、スクリャービンはついに右手を痛めてしまいました。
その頃作曲されたのが「左手のための前奏とノクターン」です。
左手だけで演奏されているにも関わらず、両手で演奏しているように聴こえるのがすごい!左手は膨大な運動量となるので、気を付けないと左手を壊すハメになる楽曲です。
スクリャービンの有名な曲と言えば、後期のピアノソナタ(7番「白ミサ」9番「黒ミサ」など)ですが、無調でかなり難解なので個人的にはこの頃の作品の方が聴きやすいです(笑)
⑥セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフ(1873- 1943)
もともとは周囲からピアニストになることを熱望されていたラフマニノフですが、10代のころチャイコフスキーの「お気に入り」だったこともあり作曲家を志すようになります。
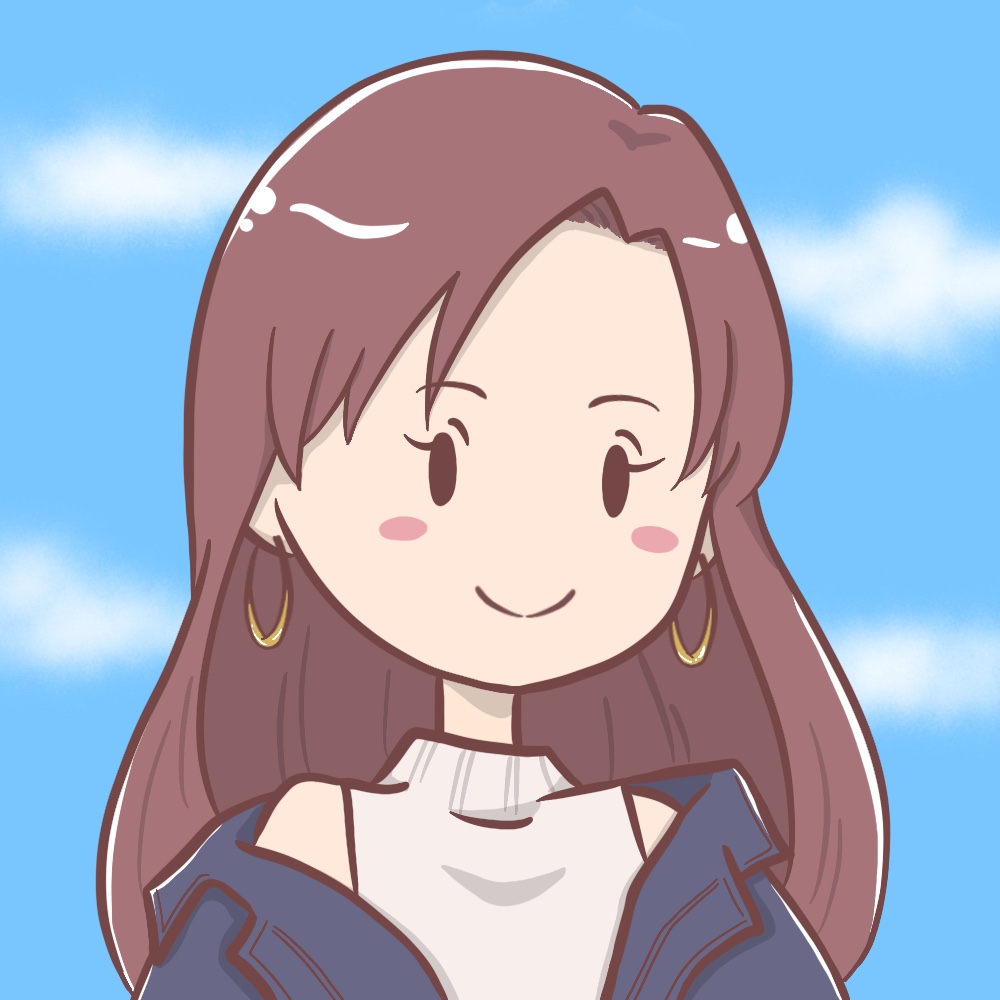
へみ
モスクワ音楽院作曲家を首席で卒業しますが、4年後に満を持して発表した「交響曲第1番」が不評に終わってしまいました。
失意のラフマニノフがスランプから抜け出したきっかけが、代表曲である「ピアノ協奏曲第2番」。数あるピアノ曲の中でも最も難しい部類に入ります。
ロシア正教の鐘をモチーフにした和音から始まる重厚なピアノ協奏曲で、ロシア民謡風のメロディやどこか皮肉めいたスケルツォなど、ラフマニノフのアイデンティティがしっかり表現されています。
参考:スコア(総譜)を見ながら聴きたいクラシック音楽10選!スコアリーディング入門
⑦ドミトリー・ボリソヴィチ・カバレフスキー(1904- 1987)
日本では「子供向けのピアノ曲」でよく名前を聴く作曲家です。
あまり和声やメロディで冒険したような楽曲が少ないのは、国家による弾圧を避けたためとも言われていて、愛国歌的な楽曲も少なくありません。
そんなカバレフスキーで一番有名なのが、組曲「道化師」の第二曲、ギャロップです。
ギャロップは「馬が疾走する様子を連想する曲」という意味なのですが、軽さとスピード感でこのギャロップ以上の楽曲はありませんよね。
日本では運動会の定番で、聴くと「走らないと…!」という気分になる人も多いのではないでしょうか。
⑧ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ(1906- 1975)
スターリンによる独裁時代や、世界大戦を駆け抜けた作曲家です。

へみ
第二次世界大戦の様子をもとに作曲した「交響曲第7番(レニングラード)」や、ロシア革命37周年を記念した委託作品「祝典序曲」など、国家の意向を汲んだ作品も多く残しています。
一方、ユダヤ系の音楽やアメリカのジャズなど、国境を越えた文化を積極的に取り入れていたショスタコーヴィチ。
スターリンの死後や終戦のタイミングを見計らい発表するなど、常に世の中に揉まれながら活動していた作曲家です。
⑨イーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィンスキー(1882- 1971)
音楽家人生のほとんどをパリやアメリカなどの「ロシア国外」で過ごしたストラヴィンスキー。
初期の作品はバロックや古典派時代を懐古するような作風でしたが、中期~後期にかけ「十二音技法」など前衛的な作風に変化していきます。
代表曲である「春の祭典」は、初演のパリで賛否両論を巻き起こした楽曲。

へみ
冒頭部は超高音のファゴットで始まるなど、これまでのオーケストレーションの常識をがらりと変えた曲だったからです。
変拍子や調性が掴めない和音進行など「難解な部分」が多く、熱狂的なファンとそうでない人がはっきり分かれる作曲家かもしれませんね。
⑩アラム・ハチャトゥリアン(1903- 1978)
ソ連の作曲家として名が残っていますが、ハチャトゥリアンは現在のアルメニア共和国出身で少しロシアとは雰囲気の違う作曲家かもしれません。
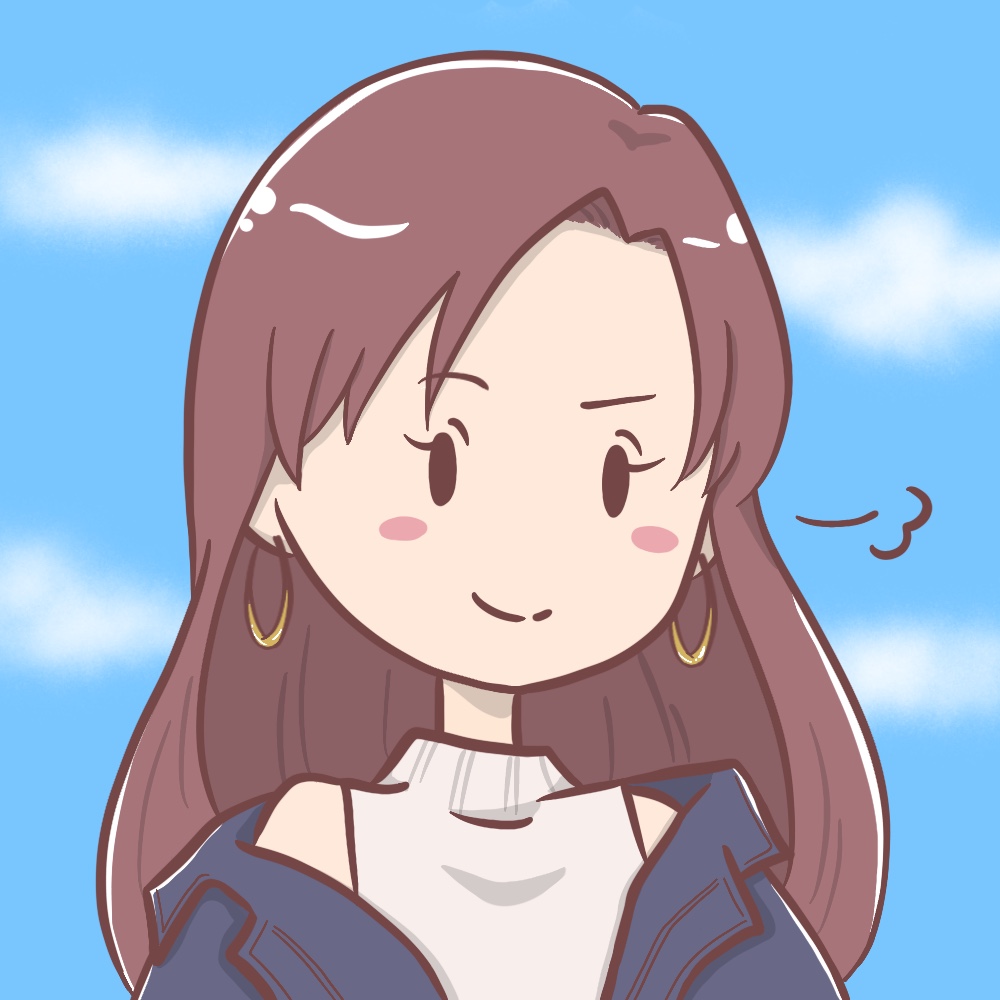
へみ
アルメニアやジョージア、アゼルバイジャンなどの民族音楽を積極的に取り入れていましたが、それが政府により粛清の対象にされてしまった時期も長くありました。
スターリンの死後は作品を発表する機会に恵まれたこともあり、次々とヒット作を生み出していきます。
代表作はオペラ「ガイーヌ」の剣の舞。ダイナミックで勢いある曲調が日本でも人気ですよね。
参考:【クラシック音楽】トロンボーンの音色の特徴と名曲10選
ロシアは作曲家だけでなくピアニストも素晴らしい
ロシアは1800年代以降、クラシック音楽を始めとする芸術が世界的に評価されています。
その中でも特に注目されるのは、作曲家だけでなくピアニストも多く輩出していること。
ロシアのピアニストたちは、恵まれた体格に由来するテクニックと情熱的な演奏で世界中の聴衆を魅了してきました。
セルゲイ・プロコフィエフ
セルゲイ・プロコフィエフは「ロミオとジュリエット」を始めとする楽曲を作曲したことでも有名ですが、ピアノ演奏も伝説級です。
十二音技法で知られるシェーンベルクの楽曲の初演を担うなど、テクニックとともに楽曲の解釈も必要とされる曲のコンサートに次々出演しました。
ウラディミール・ホロヴィッツ
ウラディミール・ホロヴィッツは現在のウクライナ・キーウ生まれのピアニストです。
ユダヤ系のホロヴィッツは祖国を離れつつ、さらにユダヤの迫害も避けなければなりませんでした。
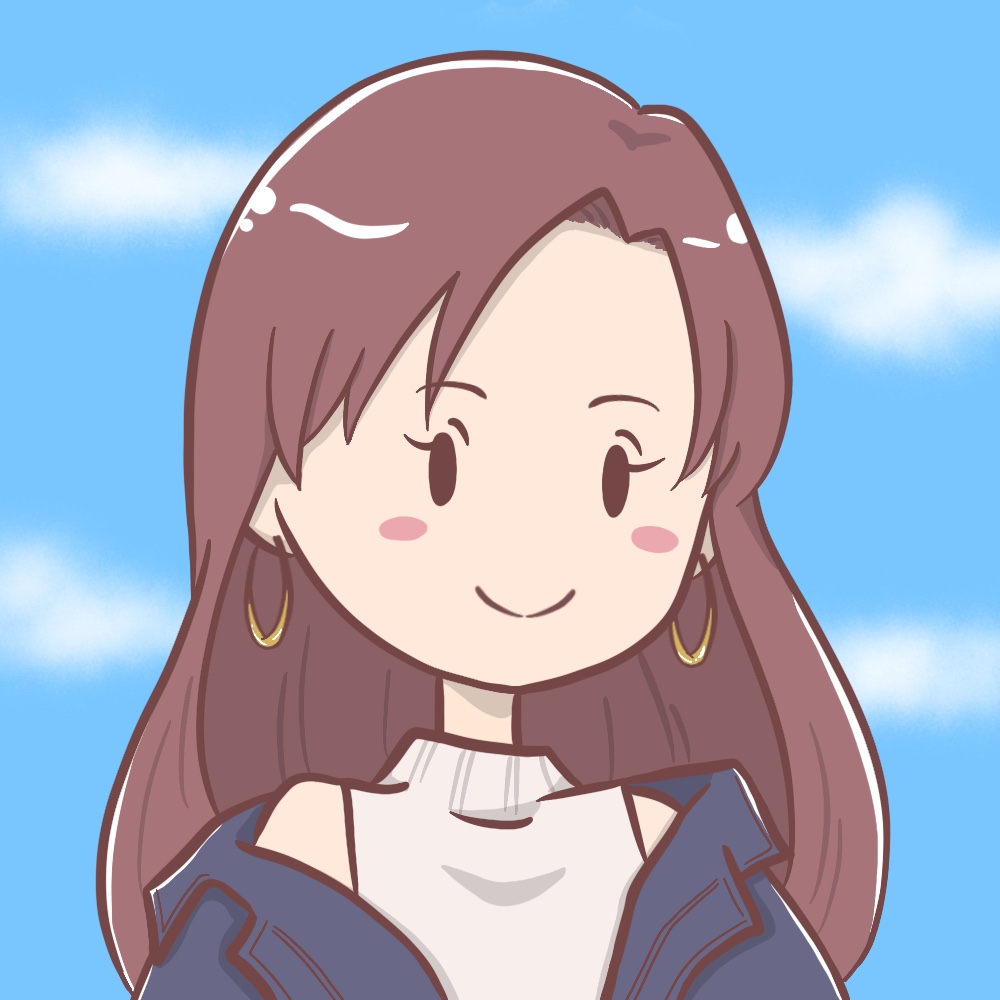
へみ
世界各地を演奏会で転々としつつ、最終的にアメリカに籍を移した苦労の人生を送っています。
演奏スタイルは「指を完全に伸ばして弾く」独特のスタイル。独自の解釈でアクセントを付けることも少なくなく、聴く人をぐっと引き込むピアニストです。
エフゲニー・ブーニン
1985年のショパン国際ピアノコンクールで一大旋風を巻き起こしたブーニン。
日本でもNHKで当時の様子が放送されたこともあり、知っている方も多いことでしょう。
審査員からは異端と称されましたが、コンサート・ピアニストとしての「魅せるセンス」が抜群です。
スヴャトスラフ・リヒテル
20世紀最高のピアニストと称されるリヒテル。
プロコフィエフと親交が深く、戦争ソナタを始めとする多数のプロコフィエフ楽曲を初演しました。
とても手が大きい事で知られていて、強弱の幅がケタ違いに広いのが演奏の特徴です。
ヴラディミール・アシュケナージ
ロシア人ピアニストがダイナミックで情熱的な演奏をすることが多いなか、アシュケナージは「繊細」「スタンダード」といったキーワードがぴったりなピアニストです。

へみ
どのレパートリーも聴きやすいので、初めて聞く曲はアシュケナージ氏の音源を選ぶと間違いがありません!
日本では洗足音楽大学で客員名誉教授を務めたことがあり、日本人ピアニストでもアシュケナージに指示した人は多いです。
ロシア音楽を聴くならAmazonミュージック
民謡風の美しいメロディが特徴のロシアクラシック音楽。一度聞いただけで虜になる曲も多くて、どんどん聴きたくなっちゃいますよね。
そんなロシア音楽を聴くなら、定額料金で音楽が聴き放題になる音楽サブスクがおすすめです。
当サイトおすすめの音楽サブスクが「Amazonミュージック」で、クラシック音楽を含め1億曲以上が聴き放題!
月額料金は1080円とお手頃で、プライム会員ならさらに安く880円となります。
今なら3ヵ月無料でお試しできるので、ぜひこの機会にクラシック音楽を楽しんでみてくださいね。















