抱え込むようにして弾く、特徴的な弦楽器のチェロ。
「人間の声に一番近い音域」と言われているチェロは、私たちの耳に心地よく響くのが特徴です。

へみ
私も年齢を重ねるごとに、低めの音域の楽器が癒しになりつつあります
そんなチェロの特徴や、チェロが活躍する名曲を厳選して解説していきます♪
目次
チェロの特徴とオーケストラでの役割

チェロは、オーケストラで活躍する4種類の弦楽器(ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス)の中で2番目に大きい楽器です。

へみ
逆に、弓の長さはヴァイオリンやヴィオラよりも4cmほど短めなんですよ
全長120cmと、小学生くらいの大きさがあるチェロなので、演奏するときは足の間に楽器を挟みこみ、両手で抱え込むようにして音を出します。
肩に負担がかかりにくいチェロなので、運動性はヴァイオリンやヴィオラとそこまで変わりません。
音と音の間隔(指のポジション)が広い、しっかり指板を押さえないといけない、という点から速いパッセージはヴァイオリンよりもやや劣ります。
チェロの音域
チェロは他のオーケストラ弦楽器と同じく4本の弦があり、開放弦はそれぞれC2、G2、D3、A3、となっています。

へみ
ちょうどヴィオラの1オクターブ下の音域となります。
一番下の音は男声バスと同じくらい、一番高い音が出るA弦は、女性が地声で出せるくらいの音域です。
さらにそこから2オクターブくらいは上の音が出せる、ということでチェロはまさに人間の声と音域が一番近い楽器とされます。
チェロの音色の特徴とオーケストラでの役割
弦が太い分、響きが豊かなチェロ。
低音域は包まれるような柔らかさが感じられ、高音域はちょっと切ないような締まった音色に感じられます。
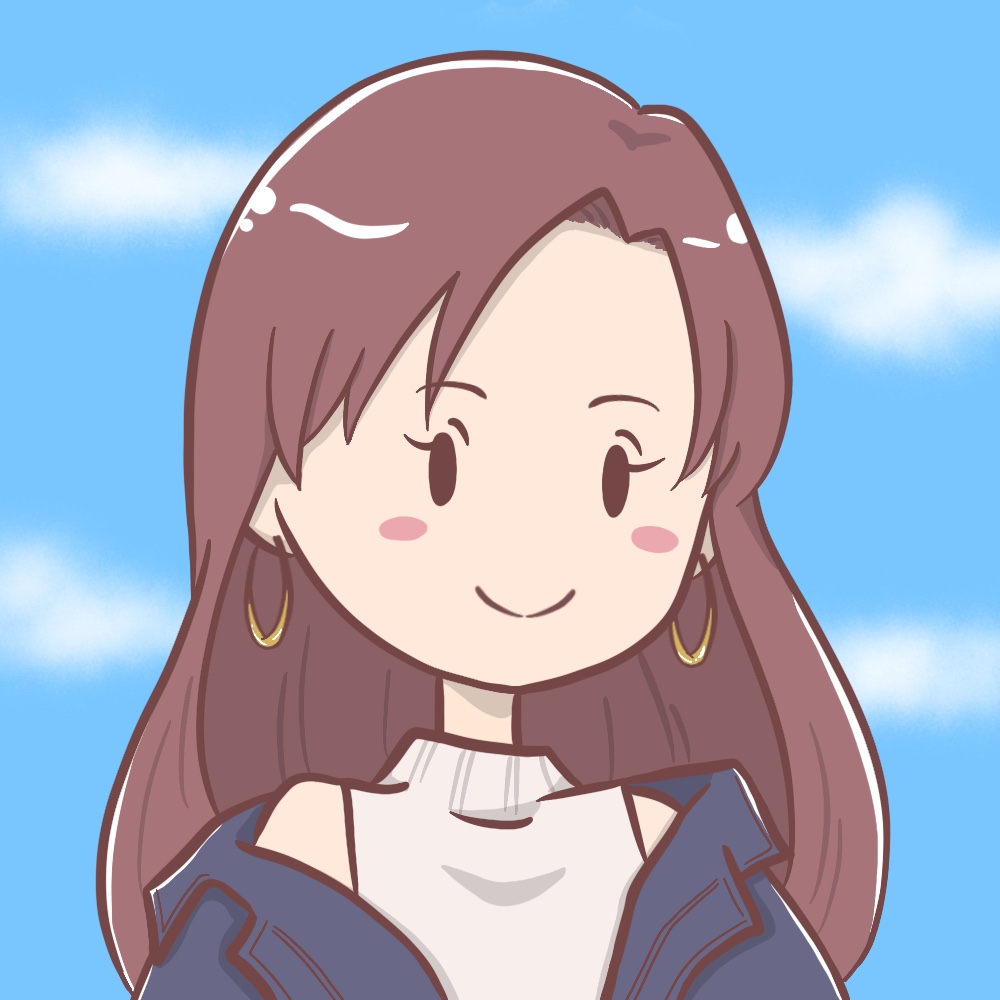
へみ
音域が人間に近いこともあいまって、人間が歌うような、表情豊かな演奏が可能です。
かっこいい・感動的・悲しい・官能的など、様々なシーンで難なく演奏できるのがチェロの強みです。
チェロの名曲10選!かっこい曲からしっとり系まで

それでは、チェロが活躍するクラシックの名曲を10曲紹介します!
チェロはソロ曲(ソナタや小品など)、協奏曲(オーケストラ+チェロ独奏)、アンサンブルやオーケストラでのソロなど、多岐にわたり目立つ曲が存在します。
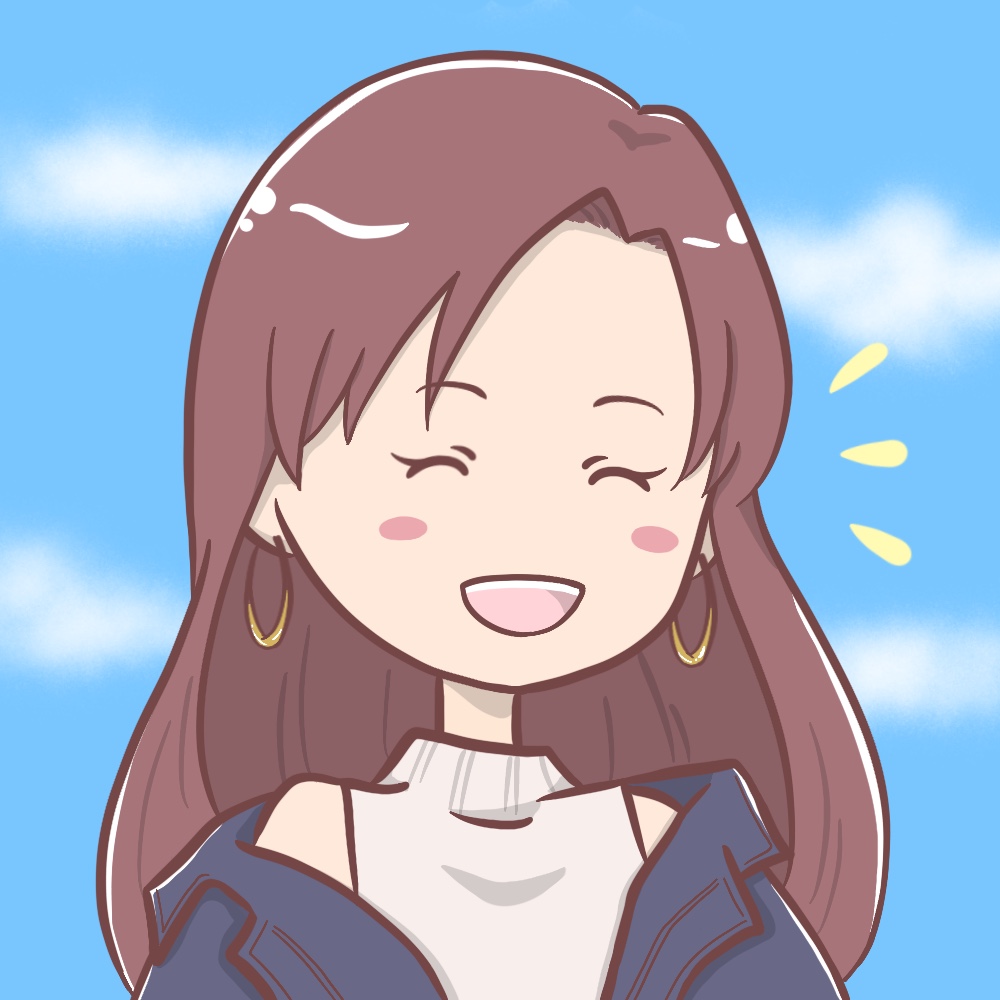
へみ
作曲家たちも、それだけチェロが魅力的だと思っていたという事ですよね♪
そんな中、初心者でも聴きやすくて美しいチェロの名曲を厳選してみたので、ぜひプレイリストに加えてみてください。
シューマン:チェロ協奏曲
もともとピアニスト志望だったシューマンですが、この協奏曲を書くために「チェロの練習をした」というエピソードがあります。
プロのチェリストには物足りない曲なのかな?と思いきや、なんと演奏できない人もいるほどの高難易度!
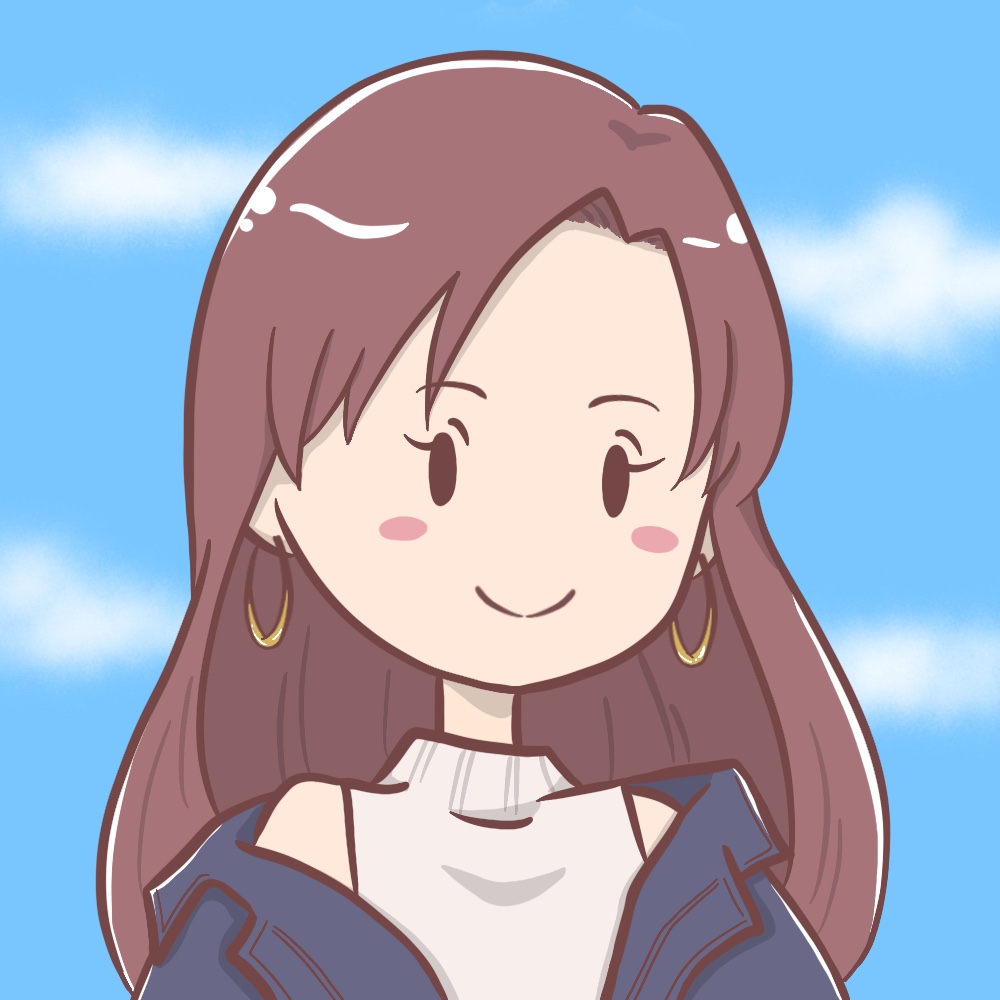
へみ
シューマンの才能の高さが伺えますね
曲調はシューマンの後期作品とあって、夢見心地の雰囲気が全体としてありながら快活、華やかさが伺えます。
コンサートピースとしても「映える」1曲で、聴いていてパッと気持ちが明るくなるような曲です。
フォーレ:チェロとピアノのためのエレジー ハ短調 作品24
エレジーとは「悲哀の歌」という意味で、恋の悲しみを描いた曲となります。
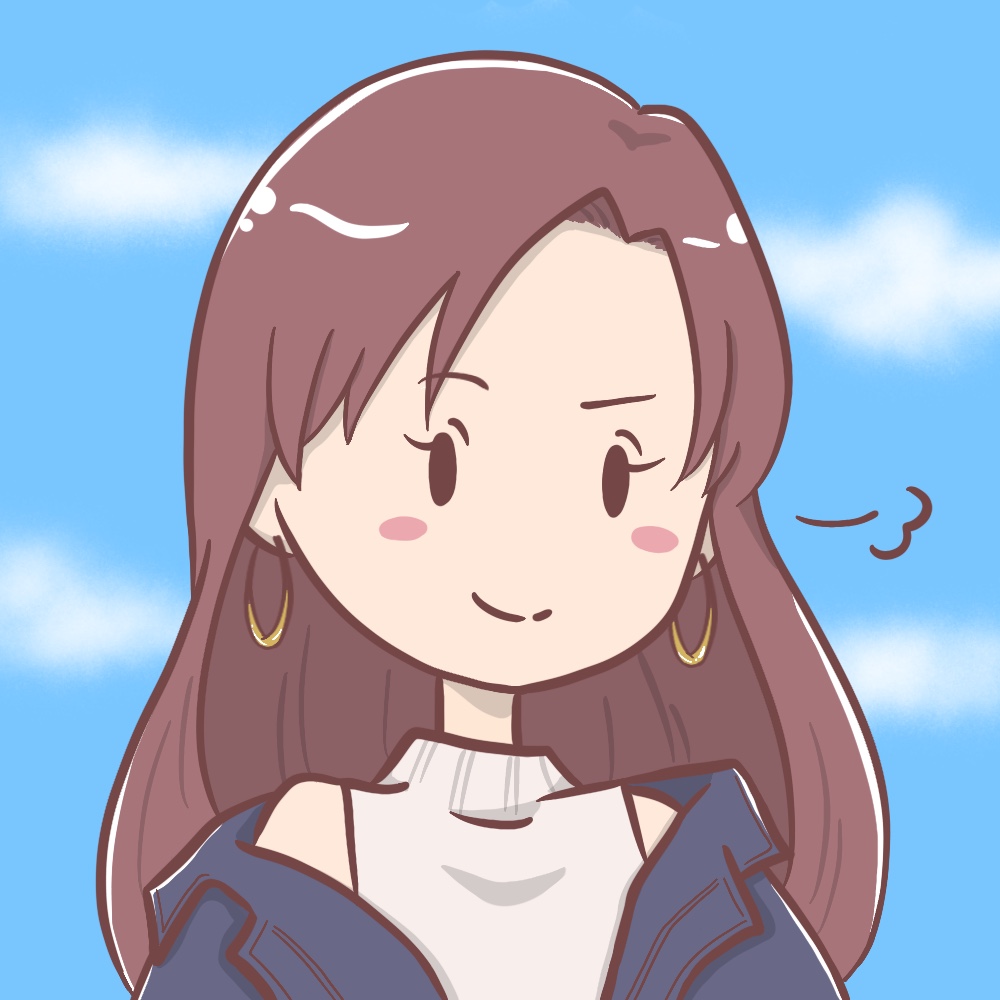
へみ
実際フォーレは、この曲が発表される2年前に婚約破棄を経験しています
その名のとおり、重く悲しい雰囲気で始まるエレジーですが、中間部の明るい部分との対比が本当に美しい。
チェロが奏でるメロディがゆったりしていて聴きやすく、チェロの美しい音色を堪能できる1曲です。
ショパン:チェロソナタ ト短調 Op.65
ショパンの作品はほとんどがピアノがメインの作品で、たった4曲だけ室内楽の曲を残しています。

へみ
そのうち3曲がチェロソナタ。ショパンがいかにチェロを好きだったかが分かりますよね。
このチェロソナタは、ショパンの友人チェリストに贈られた曲なのですが、チェロ+伴奏ピアノという感じではなく「ピアノもチェロも主役」といった構成です。
常にチェロとピアノが役割を交代しながら演奏するので、たった2人での演奏ですが聴きごたえ抜群。
きっとショパンも、友人チェリストとの共演を夢見ていたことでしょう。
チャイコフスキー:ロココの主題による変奏曲
ロココ、とは18世紀のフランスで流行した美術様式のことです。
繊細、という言葉がぴったりなロココ風の主題をもとに、8つの変奏が繰り広げられます。
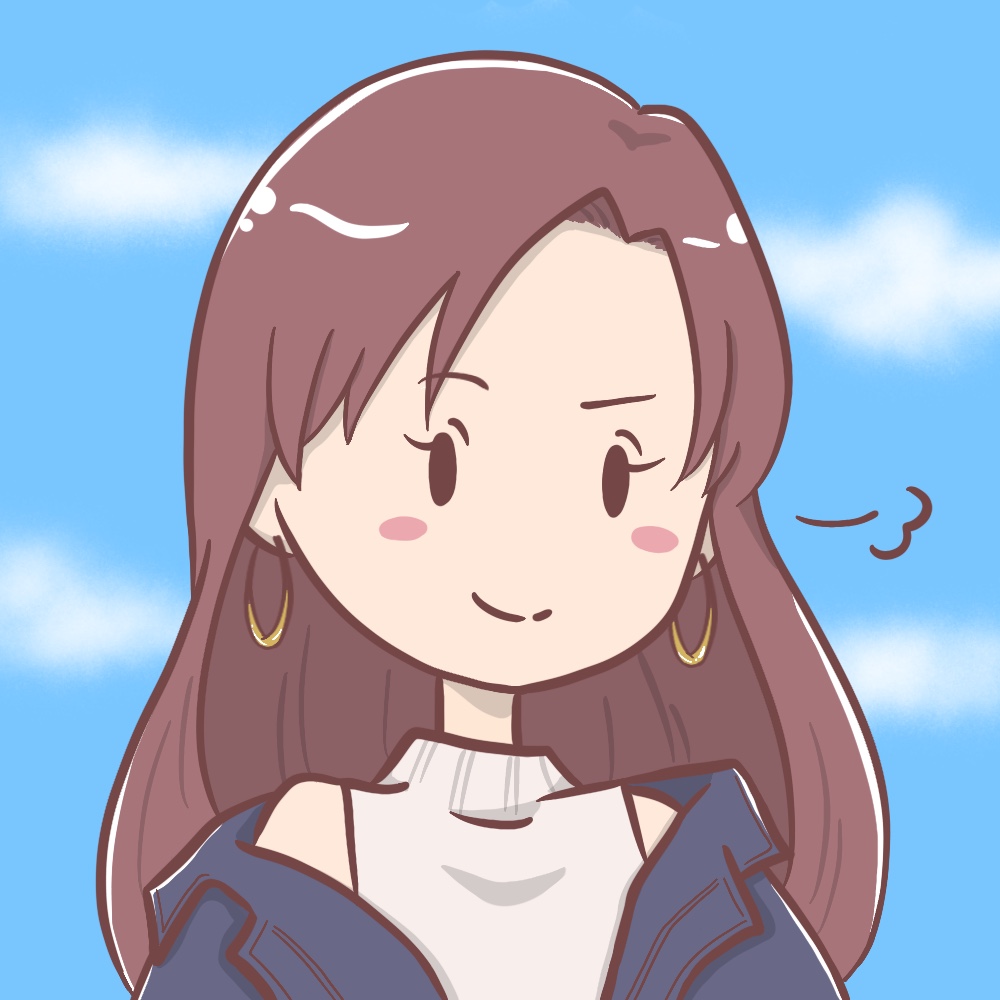
へみ
原曲は8つの変奏曲でしたが、初演時にチャイコフスキーの友人チェリストが大幅な改定の末削除してしまいました。なんてことを…
変奏していく中で、チェロが悲しげな表情をみせたり、うきうき弾むように演奏したりと、コロコロ音色が変わるのが面白い曲です。
チェリストにとっては表現力がかなり求められる曲で、チャイコフスキー国際コンクールの課題曲として長年採用されています。
ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番
現在演奏されるブラームスの作品は、晩年の作品が多く取り上げられます。

へみ
特に交響曲は、第1番が43歳の時に初演だったので、2番~4番も壮年期~晩年の作品です。
ですがこのピアノトリオはブラームス20歳の時の作品。ですが、晩年の「ブラームスらしさ」がすでににじみ出ています。
ピアノの主題を追いかけるように、そっと同じメロディを弾いて入ってくるチェロ。優しくて、それでいて重厚なブラームスを表現するのにチェロは欠かせない存在です。
サン=サーンス:動物の謝肉祭より「白鳥」
全14曲の小品からなる組曲の「動物の謝肉祭」。

へみ
最も有名な白鳥は、13曲目にピアノとチェロで演奏されます。
もともとこの組曲はサンサーンスの友人のチェリストがホームパーティーを催すということで、余興のために作曲された音楽です。
友人チェリストへの敬愛ともとれるこの「白鳥」は、チェロらしい悠々とした響きが活かされていますよね。
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番
こちらの曲はテレビCMなどでもよく流れるので知っている方がほとんどではないでしょうか。
チェロたった1本で演奏されるのに、メロディも伴奏も感じられるのはすごいことですよね。
重音(2つ以上の音を同時に鳴らす)の響きが重厚なチェロなので、バロック音楽の厳格さ、上品さ、といった雰囲気が感じられます。
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調
急・緩・急の3楽章からなるチェロ協奏曲で、様々なオーケストラ曲のなかでもファンが多い曲です。

へみ
あのブラームスも、ドヴォルザークの協奏曲を聴いて感動したという記録が残っています。
重厚な1楽章、感情があらわになった2楽章、ボヘミアや黒人の民族音楽がふんだんに盛り込まれた3楽章、それぞれ性格は違えど、見事にチェロの魅力にマッチしています。
プロコフィエフ:チェロソナタ
1947年発表の、プロコフィエフ晩年の作品です。

へみ
ジャンル的には近現代の音楽となるので、少し難解に感じる方もいるかもしれません。
ソナタというと、前述のドヴォルザークのように急・緩・急という楽章の組み合わせが多いのですが、この曲は緩・急・急という感じで終盤に行くほど軽やかになっていきます。
最初は軍隊的で重たい1楽章から始まるのですが、2楽章はチェロのテクニカルさが要求されるスケルツォ、3楽章は明るくロシアらしい飄々とした雰囲気が漂っています。
ベートーヴェン チェロソナタ第3番
貴重なベートーヴェンの室内楽曲の一つであるチェロソナタ。
作曲された時期は中期で、古典的技法が主だった初期のころに比べて大胆な表現が多く使われています。
チェロソナタ1番、2番に比べてチェロの運動域がぐっと広がり、ピアノと対等に渡り合うチェロの魅力といったら!
すっきりまとまった構成とは裏腹に、内容の濃いソナタです。
チェロが活躍するオーケストラ曲5選
続いては、チェロ主体の曲ではないものの、曲の中でチェロが大活躍する曲を5つ紹介します♪
シューベルト 交響曲第8番「未完成」より第1楽章
物悲しいオーボエの第一主題と対比するように、チェロが第二主題を奏でています。
歌曲の王、と呼ばれたシューベルトらしい、歌うような旋律が魅力的ですよね。
チェロはヴァイオリンやオーボエ・フルートと対比するように書かれている部分が多く、曲の雰囲気を上手く変えるために重要な役割を担っています。
ハイドン 交響曲第31番 4楽章
4本のホルンが活躍するので「ホルン信号」とも呼ばれる交響曲です。
この曲の4楽章は変奏曲になっていて、弦楽器による主題→オーボエ(第1変奏)→チェロ(第2変奏)…と曲調を変えて発展していきます。
この第2変奏のチェロ独奏は、他の楽器に合わせてかなり高い音域でのソロ。
同じ音域をヴァイオリンやヴィオラで弾くときっとしゃがれてしまうのですが、チェロらしい艶っぽい音色が楽しめます。
ベートーヴェン 交響曲第9番 4楽章
上記の動画でいうと3:30くらいに「歓喜の歌」の有名なメロディが登場します。
このメロディを提示しているのが、チェロとコントラバス。意外ですが、こんなに穏やかに登場するんです。
その後も歓喜の歌のメロディが続きますが、チェロとは他の楽器が演奏するメロディに対比するメロディへと変化していきます。
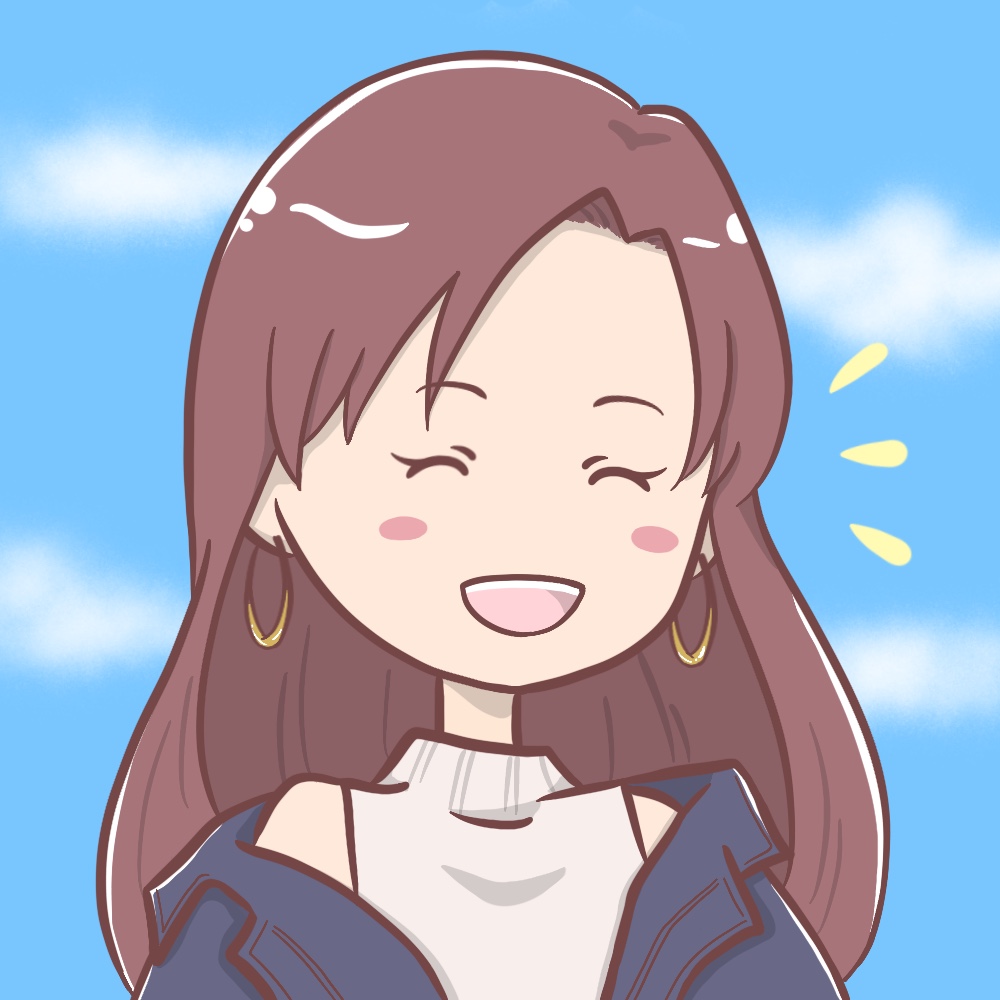
へみ
ついつい歓喜の歌が耳に入ってしまいますが、ずっとチェロを聴き続けていると「こんなメロディだったんだ!」と発見があるかも♪
ブラームス ピアノ協奏曲第2番 3楽章
ピアノ曲史上最高の協奏曲とも称されるピアコンです。
この曲でチェロが活躍するのは3楽章。冒頭がチェロの優雅なソロで始まり、楽章通じて「第二のソリスト」として活躍しています。
チェロに限らず、ブラームスらしい暖かさ、ロマン派時代らしいロマンティック感、素晴らしいオーケストレーションによる華やかさ、どれをとっても素晴らしいので、ぜひ全曲通して聴いてほしい1曲!
R.シュトラウス 交響詩「ドン・キホーテ」
シュトラウスのドン・キホーテは、独奏チェロ=ドン・キホーテ(独奏チェロ=従者サンチョ・パンサ)として描かれています。
まさに主役級!チェロ協奏曲とも取れそうな交響詩です。
冒険の旅に出るドン・キホーテの姿がチェロの猛々しい演奏にぴったりですよね。
【番外編】CMで使われたチェロのかっこいい曲
続いては番外編!
とにかくかっこいい!に焦点を当てた、チェロの有名曲を紹介します。
ピアソラ:リベルタンゴ
もともとはチェロに書かれた曲ではありませんが、世界的チェリストのヨーヨー・マの演奏が世界的にブームを巻き起こしました。

へみ
日本ではサントリーのCMで使われたのが人気のきっかけです
強いビートに耐えうる歯切れよさ、センチメンタルなメロディを自在に表現できる音色、という事で、今ではチェロの欠かせないコンサートピースになっています。
2CELLOS 影武者
テレビで流れてすぐ世の中がざわついた、伝説のCMです。
2人のイケメンチェリストデュオ”2CELLOS”は、テレビ番組に引っ張りだこになりましたよね。
残念ながら2022年に解散してしまいましたが、それぞれソロでクリエイティブな活動を続けています。
久石譲 Oriental Wind
日本のかっこいチェロ曲といえばコレ!
久石譲さん作曲のOriental Windには、チェロバージョンのアレンジもあって、実際にCMで流れた時期もありました。
洋風の楽器を使っているのに、なぜか日本の古き良き時代を感じさせる久石氏の感性には脱帽です。
チェロの名演奏を聴くならAmazonミュージック
作曲家、クラシック音楽ファン、どちらからも大人気のチェロなので、CDを探すと膨大な数の音源が出てきます。
その中から「自分がしっくりくる」音源を探すのは至難の業。
そこでオススメなのが、月額料金で聴き放題となる音楽サブスクです。
当サイトおすすめの音楽サブスクが「Amazonミュージック」で、クラシック音楽を含め1億曲以上が聴き放題!
月額料金は1080円とお手頃で、プライム会員ならさらに安く880円となります。
今なら3ヵ月無料でお試しできるので、ぜひこの機会にクラシック音楽を楽しんでみてくださいね。


















